しまった、バレた。
そう独り言を洩らしてレンはまあいいかと立ち上がる。
事が発覚する前に逃げる・・・いつものパターンだ。
「夜逃げはそろそろ勘弁したいんだけど・・・っと、リン!」
暗い部屋の中、双子の姉を呼ぶ。
大体この事態を引き起こしたのは彼女なので道中しっかり謝ってもらう必要があった。
「リン?おい、リン!」
いつもならすぐ飛び付いてくるはずのリンが来ない。
首を傾げながらもレンは小さなペンライトの先に光を灯した。
「何やって・・・。・・・は?」
姿を認め声をかけようとし・・・思わず固まる。
リンは双子・・・つまりレンとは同じ年齢のはずだ。
だが。
不思議そうな顔でレンを見上げているのは。
紛れもなく。
「赤ちゃん・・・?」
呆然と呟く。
幼女が包まっているだぼだぼの服は確かにリンのものだ。
間違えようもない。
「・・・って、固まってる場合じゃない!」
ガタン、という音にレンははっと我に返った。
事が事だ、いつ家に押しかけてくるか分からない。
取り敢えず、とリン(であろう幼女)を抱え上げ、レンは作っておいた裏口の戸を開けた。
「此処が見つかんのも時間の問題・・・うぉあ?!」
「うわっ」
飛び出そうとした瞬間、誰かとぶつかりよろけた。
もうバレたと一瞬ひやりとしたがそうではないらしい。
「わりぃ!大丈夫か、あんた」
「あ、はい。・・・なんとか」
手を差し出すと尻餅をついている相手は笑みを浮かべながら答える。
あれ、と思った。
「・・・っと・・・。ほら、手ぇ出して」
「はい」
出された手をぐっと引っ張って立ち上がらせる。
相手・・・蒼髪の青年は思った以上に軽かった。
「悪かったな」
「いえ、こちらも悪いですし」
にこりと笑う青年に落ちていた大きいボストンバックを手渡す。
それはあまりに不釣合いに見えた。
「なあ、それ何入ってんの?」
「ああ、これですか?・・・っと」
レンが覗き込んだ瞬間、リンがぐずりだした。
今はともかく、これ以上大きな声で泣かれるのは拙い。
「うわっ、ちょ、もう・・・」
「・・・お腹がすいているんじゃありませんか?」
「へ?」
青年の思いがけない言葉にぽかんとそちらを見る。
ちょっと待ってくださいね、と青年は微笑み、バックの中から何かを取り出した。
その場に座り込み、何やらかちゃかちゃとやっていた青年がレンを見上げる。
「どうぞ」
差し出されたのは哺乳瓶だった。
ぎこちなく礼を言って受け取り、リンの口元に近づける。
しかし、それ以上がどうやって良いか分からなかった。
「・・・ええと、お願いしていいッスかね・・・?」
「いいですよ」
微笑む青年にリンと哺乳瓶を渡した。
柔らかくリンを抱っこした青年はレンとはまったく違う手つきでミルクを飲ませていく。
「すげぇ・・・!プロみたい!」
「あはは、有り難うございます。一応、ベビーシッターをやっていたもので」
にこやかに言う青年にレンはなるほど、と思う。
「そういやあんたどっから来たの?」
「・・・。向こうの、お屋敷です」
「向こうって・・・斜向かいの豪邸?!!」
「はい」
寂しそうに青年が微笑んだ。
「あなた方は、何処かへ行かれるのですか?」
「・・・え?あ、うん・・・まあ」
今度は青年から聞かれ、レンは曖昧にそう答える。
「でしたら、一緒に連れて行ってはくれませんか?」
「へ?」
きょとんとするレンに青年は飲ませ終わった哺乳瓶をカバンに戻しながら少し困ったように言った。
「実は・・・あの、気づいているかもしれないんですけど、目が見えなくて。それで、外に出る必要のないベビーシッターとして雇っていただいていたのですが、どうしても、その、男性、というか・・・旦那様が苦手で」
「・・・で、逃げ出してきたの?」
「・・・そんなところです、かね」
曖昧に微笑む青年の青い目には確かに光がない。
成る程、今までの行動全てに合点がいった。
「・・・あの、さ」
「はい?」
「旦那様が苦手ってさ・・・」
「はい」
首を傾げるいたいけな青年にドキドキしながらレンは切り出す。
豪邸に住む男、外に出られない青年・・・。
思春期の少年がする想像ではさもありなん、目の前の青年に言えないあれそれが頭を駆け巡る。
「ぐ、具体的には・・・!」
「その・・・低い声が、苦手で」
「・・・あ、そうッスか」
照れたように言う青年にレンは「ですよねーー!」と思いながらもそう返した。
「それで・・・あんた何処に逃げる気だよ?」
「・・・それは・・・まだ」
困ったように青年が笑う。
あまり計画性は無いらしい。
よくそれで逃げようと思ったものだ。
『おい、いたぞ!!』
「・・・んげ」
突然響く声と照らされる光にレンは嫌そうな顔をした。
どちらの追っ手かは分からない・・・が誰かにばれてしまったらしい。
「取り敢えず、こっち!」
「え、あ、はい!」
座り込んだままの青年を引っ張ってレンは走り出した。
なりふり構っていられない。
取り敢えず走り続け、近所の公園に逃げ込んだ。
「・・・あー・・・もー・・・」
息を整え、脱力しながら隣の青年を見る。
「・・・大丈夫?」
「・・・は、い・・・」
彼のほうも息を整えながら弱々しく微笑んだ。
ここまで来てしまっては仕方がない。
じゃあ此処からは別行動、とも言えなかった。
「おれは鏡音レン、そっちはリン。訳あって夜逃げ中。あんたは?」
「・・・カイト、始音カイト、です」
「ん、カイトな。取り敢えず3つくらい隣の町に行きゃ大丈夫だろ、あそこでかい病院と研究所があるし、リンを見てもらえるかもだし・・・」
「あ、あの・・・?」
「カイト。そこまで一緒に逃げよう。おれはあんたのサポートをするからあんたはリンの世話をしてくれ。どうだ?」
「・・・はい!」
レンの提案に青年・・・カイトがぱあ、と微笑む。
カイトの腕の中でリンがきゃっきゃと笑った。
「それじゃあ宜しく、カイト」
「こちらこそ。宜しくお願いします、レン君」
差し出された手を握る。
この青年と一緒なら夜逃げ人生も悪くないかな、と思った。
ーー
診断メーカーで出た『盲目のベビーシッターと夜逃げ常習犯のご近所さんが、強制的に運命共同体になってしまう話』 でした。





![メニコンフィット15ml (コンタクトレンズ装着液) [指定医薬部外品]](https://m.media-amazon.com/images/I/412WMDeR58L._SL160_.jpg)
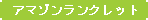
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments