狼少年と赤色少女~少女視点(Alice mare・ジョシュア×チェルシー/チェシャ猫ルートその後/ネタバレ注意
長い夢を見ていた気がする。
どんなユメだったっけ、と少女は小さく首を傾げた。
確か誰かと一緒に花占いをして、少し気味の悪い猫に出会って、それから。
そこまで思い出してチェルシーは小さく身を震わせた。
何かとても嫌なものを見た気がする。
考えれば考えるほどに頭がぐるぐるして、チェルシーはその行為を一旦やめた。
ベッドから出るとひやりとした冷たさが床から裸足の足を通して伝わる。
これはユメではないのだと少しだけ安心した。
「・・・みんなは?」
ふと、どの部屋からも声が聞こえないことに気付き、チェルシーは再び首を傾ける。
自身の部屋から出て、隣の部屋をノックした。
「レティちゃん、リックくん・・・いる?」
声をかけても中からは声は返ってこず、ほんの少し不安感を覚える。
悪いことをしてることをするわけじゃないし、と、チェルシーはそっと中を覗きこんだ。
もしかすれば寝ているのかもしれない。
「・・・あれ?」
予想に反して彼女らは部屋にはいなかった。
遊びに行ったのかな、とチェルシーは扉を閉める。
勉強が嫌いなレティのことだから部屋にいなくても不思議じゃないけれど、とチェルシーはクスリと笑った。
「ジョシュアくん」
もう片方隣の部屋の主にも声をかけ、声が返ってこないことを確認してからそっと中を見る。
異性の部屋を見るのは抵抗が無い訳じゃなかったけれど、不安感には抗えなかった。
「・・・いない、の?」
彼の部屋もがらんとしており、チェルシーは表情を曇らせて扉を閉める。
もしかすると、レティたちと共に遊びに行ってしまったのかも、とチェルシーは考えることにした。
また先生にイタズラするために虫を集めているのだろうか。
チェルシーは虫が怖いので、凄いなぁと純粋に思う。
「・・・ステラ、ちゃん?」
その隣、大人びた少女の部屋も控え目にノックしてからひょこりと顔を覗かせる。
「・・・え?」
しかし彼女もそこにはいなかった。
ステラはあまり外遊びはしたがらないから、部屋にいると思ったのだけど。
「・・・」
流石におかしいかも、とチェルシーはそこから出て一番端の部屋の扉をノックした。
「アレン、くん」
覗きこんでも彼はいない。
少しだけクローゼットが開いているのが気になった。
そういえばユメの中で一緒にいたのは彼だったのではなかっただろうか。
「・・・先生、は?」
それについて深く考える前に、大人にすがろうとチェルシーは思い立つ。
彼ならこの不安感を何とかしてくれるだろう。
「・・・ひっ」
玄関ホールに出た途端、チェルシーは言いようもない不快感に足を竦ませた。
気持ちが、わるい。
「い、いや・・・!」
嫌いな虫がいるわけでもなし、何がどうなのか分からないけれど、とにかく嫌だった。
縺れそうになる足を必死で動かす。
ノックも忘れてその部屋に飛び込んだ。
「・・・せん、先生・・・!」
息も絶え絶えに部屋を見渡す。
いない。
夜中だって優しく出迎えてくれたはずの彼が、いない。
ぞわりと背筋が粟立った。
「どうして・・・?!」
踵を返して二階に上がる。
図書室にも、倉庫にも、誰もいなかった。
ついでに一階の食堂やキッチン、浴室も見れることが出来る部屋は全て見て回ったけれど誰もいなかった。
がらんとした部屋はあまりにも怖い。
自室に逃げ帰ってテディベアをぎゅっと抱きしめる。
しばらくそうしていたところでいくらか気分が落ち着いた。
そうだ、中庭にいるのかも、とチェルシーはそこを出る。
「え?」
突如聞こえた、なぁん、と言う声に振り返れば金色の猫がアレンの部屋の前にいた。
猫はもう一度鳴いてからするりとアレンの部屋に入っていく。
「ま、まって!」
慌ててチェルシーは猫を追いかけて部屋に入った。
不自然に開いたクローゼットの前で猫が佇んでいる。
ここに来ればもう帰れないぞ、というように。
じゃあどうすればいいの、とチェルシーは途方に暮れた。
クローゼットの前まで行ってへたりこむ。
おいで、と誰かの声がした。
顔を上げて、震える手で取っ手を掴む。
ふわりと体が浮いた・・・気がした。
恐らくは気のせいだろう。
現実的に考えたら有り得ない。
だってここはユメじゃないもの。
・・・じゃあこの景色は何?
自問自答をしてからチェルシーは立ち上がる。
何も見えない場所だった。
金の猫も、クローゼットも、何も。
「・・・ねこ、さん」
そっと呼びかけるがもちろん返事はない。
下手に動き回れば迷子になりそうで怖かった。
迷子も何も足がすくんで動けなかったのだけれど。
辺りを見回してスカートをぎゅっと握る。
ぽたりと涙がこぼれ落ちてからはもうダメだった。
抑えていた感情が嗚咽となって溢れ出る。
怖い、と吐き出した小さな少女はもう限界だった。
「・・・チェルシー?」
かけられた声にはっと顔を上げる。
「・・・アレン、くん」
金のくせっ毛に綺麗な翠の瞳。
間違いなくアレンだ。
「どうしたの?」
「アレンくん、わたし、わたしね・・・!」
近づいてくる彼にチェルシーは言葉を紡ぐ。
少しだけ表情を曇らせたようにみえた彼が笑った。
「大丈夫、大丈夫、ダイジョウブ。ほら?」
彼なりに気を使ってくれたのだろう、その優しさが嬉しい。
先生みたい、とチェルシーも小さく微笑んだ。
手を差し出す彼に手を伸ばす。
でも、あれ、彼はこんなツギハギの服を着ていたっけ。
「チェルシー!!!」
「!ジョシュアくん・・・?!」
こてりと首を傾げたチェルシーに聞こえてきたのは鋭く自分を呼ぶ声。
「そいつはアレンじゃない、だまされるな!」
怒鳴る少年にチェルシーはびくりと肩を震わせる。
少年、ジョシュアは確かに色んな嘘をつくけれど、そのどれとも違った。
何より彼の表情が真剣で、伸ばしかけた手が落ちる。
「なんだ。なんだなんだ。気付いちゃったってわけ?」
くすりとアレンが笑った。
「気付かなきゃ幸せだったのにな。アリスも、アリスも!」
「っ、やメろよ!!」
「気が付くから傷付くのさ。両手で覆っていれば今のままでいられたのに!」
激昂する帽子をかぶった少年に対して愉快そうに笑う、この人は誰?
「いいか。チェルシーに近付くな」
「近付く?先に触れたのはアリスの方さ。棘があるのも全部知ってて手を伸ばした。そうだろう?」
にやりとアレンの顔した誰かが笑った。
ぞっとして思わず後ずさる。
「無闇に触るなって言われなかったかい?アリス」
不自然に口の端を持ち上げてチェルシーに手を伸ばしてきた。
何かが光る。
身体は、動かなかった。
「やメろ!!!!!!」
聞き覚えのある音が聞こえる。
彼の身体が傾ぐ。
とさり、と彼の帽子が落ちた。
赤、朱、緋、紅、あか。
目の前に広がる、アカ。
ぴしゃりと少女の白い肌にあかいろが付いた。
オオカミがおばあさんを●●た。
おとうさんがオオカミを●●た。
じゃあ、今は?
今は
誰が
アカイロになってしまったの?
「いっ・・・いやぁああああ!!!!」
よろけた弾みで地に足をつける。
どうして。
頭を抱えて何度も問いかけた。
震えが止まらない。
これは夢なの、現なの。
チェルシーは暗闇に質問う。
「アリスはこれが都合の悪いユメだと思うかい?それともおかしな白昼夢?ああ、どちらもユメさ。アリスがそう言うならね!」
甘い声だった。
これをユメだとすれば、きっと醒めてくれる。
いつも通り、レティがいてリックがいてステラがいてアレンがいて先生がいて、それから。
「ジョシュア、くん?」
「チェル、シー?」
あかいろじゃない、彼が、蒼の少年がいるはずだ。
そう、こんな風に。
・・・こんな風ってなに?
どうして彼はあかをまとっているの。
「・・・ぁ・・・あ・・・!」
直視した現実はチェルシーの中の何かを壊すのに充分だった。
いやいやと首を振る。
バラバラになってしまう。
彼が、あの時のオオカミのように。
あの時、わたしはどうしたんだっけ。
わたしの所為であかいろに染まったオオカミを、わたしはどうしたの?
ガタガタと震えながら終いこんだ筈の暗い過去を掘り起こす。
思い出せばきっと戻れない。
・・・それでも。
「・・・知りたいかい?アリス」
アレンに良く似た誰かが笑った。
あかいろの少年から目をそらして少女は頷く。
「逃げたのさ。現実から目をそらして!全部責任を誰かに押し付けて!」
「!」
「何を驚く?今もそうしているだろう?アリスの常套手段だ。違うかい?」
「・・・い、や」
「さあ、観てご覧よ。目の前のゲンジツとやらをね。実に愉快じゃあないか!」
アレンに良く似た誰かが指を差した。
あかに塗れた少年が、チェルシーに向かって無理した笑みを向ける。
ぎゅっと目を閉じても瞼にの裏にその光景が浮かんだ。
やめて、もう・・・ミタクナイノ。
「ユメの国から帰ったアリスはゲンジツの絶望を知るのさ。そうしてユメに引きこもる!自分で選んだ選択肢をこれじゃないと投げつけてね。・・・違うかい?」
にやにやと目の前の『それ』が金髪を揺らして笑う。
この声を聴きたくない。
両手で耳をふさぐ。
声は一瞬だけ薄くなり、代わりに自分の声が響いてきた。
どうしてこんなことになってしまったの。
ねえ、どうして。
選んだ花が悪かったの?
花占いの結果が不幸だったから?
・・・そもそも花占いなんてするから・・・?
「みるなっ!!!!!!」
ぐるぐる巡る意識の中で声がした。
ああ、そうか。
チェルシーはぼんやりと思う。
メを、閉じてしまえばいいんだ。
そうすれば何も見えないから。
もう何も、見ずにすむから。
チェルシーはメをとじる。
聞こえてきた悲鳴のような何かを、なかったことにして。
おやおや、と嘲笑を含んだ声が聞こえた、気がした。
「自分の都合の悪いことはひた隠しってわけ?傍観者が最も悪いことを知ってるんだ、なぁアリス!」
けたけたと誰かが嗤う。
「俺は騙るぜ、語り部がいなきゃ困るだろ?そもそも私がいなきゃアリスだって困るはずさ」
決めつける様に、なあそうだろ?とツギハギのそれが哂った。
「眠る前に物騙りを聞かせてあげよう。・・・むかーしむかしあるところに一人の少年がいたのさ。少年はある時嘘をついた。兎が喋ったんだよ、とでも言ったのかな。周りの人間はまたかと相手にしなかった。少年の嘘は慣れっこだったからね。少年は誰からも相手にされなくなった」
至極楽しそうに誰かが語る。
「少年は誰かに話を聞いてほしくて嘘を吐き続けた。そのうち、少年にも何が真で何が嘘か分からなくなっていったのさ。少年は言ったよ、兎を捕まえてね。"きみが喋ればぼくはウソツキなんて言われずに済んだのに”ああ全く責任転嫁も甚だしい!!」
聴きたくもない、雑音のような街頭演説よろしくそれは噺続けた。
物語はもっともっとみんなが幸せでなければならないのに。
花は綺麗であって、水は澄んで、みんな笑っていて。
こんな・・・こんな幸せが見えない末路なんて、聴きたくない。
そう思うのにアレンに良く似た誰かは騙るのをやめなかった。
まるでこれが少年少女の末路だとでもいう様に。
「そうして少年はどうなったと思う?コロされたのさ!少女に嘘を吐いた罪でね。少年は少女にぼくはオオカミですと言った。少女はオオカミは全員悪いのだからシンでと言った。ただ話を聞いてほしかっただけの少年は、少女に触れる事すらなく淘汰され見ていることも叶わなくなった。・・・素敵な話だろう?」
優しい笑みを浮かべるそれは、漸くアレンの風貌を見せた。
変なの。
混乱する頭にふっと浮かぶ、それ。
話くらい聞いてあげればいいのに。
「・・・やっぱり。君はこの物語を聞いて尚、結末を書き換えようとするだろうね。そのエピローグがメリーバットエンド一直線だとしても、君は進み続けるのかな?アリス」
「花占いの結果なんて、最初から分かっているだろうに!それでも確かめずにはいられないの?直視したって、なんのかんの言って誤魔化すくせにさ!」」
「君らは俺らを悪魔、なんて呼ぶけれどもね。私からすれば君らのほうがよっぽど悪魔のようだよ。誰かを巻き込んでまで悲劇を喜劇に変えようとするのだから!」
くすくすとセカイに広がる笑い声。
ふわりと手に誰が触れた。
あたたかいな、と思う。
「オオカミさんは、しななきゃいけないの?」
「ちがうよ。オオカミはただ、はなしをきいてほしかっただけだ。・・・それでしんでしまったとしても、はなしをきかないほうがわるい」
「そう・・・そうだよね」
「チェルシーは、オオカミのはなしをきいてくれる?」
優しい声だった。
チェルシーはこくりと頷いて微笑む。
見えなかったけれど、きっと彼も笑ったはずだ。
「てを、はなさないでね」
ジョシュアくん、と彼の名を呼ぶ。
彼が頷いたのが気配で分かった。
「優しい嘘が最終的にどうなるか知ってるかい?忌しい夢さ」
暗いセカイに響く声。
少女の意識はふつりと途切れる。
「堕ちておいで、チェルシー。僕の中にね。・・・セカイにようこそ!!」
長い夢を見ていた気がする。
どんなユメかは忘れてしまったけれど。
だって、ねえ。
少女はもう醒めないのだからー・・・。
 赤い熊さん限定特典:A4サイズブロマイドセット(5枚)](https://m.media-amazon.com/images/I/31o198xDsHL._SL160_.jpg)
 赤い熊さん限定特典:A4サイズブロマイドセット(4枚)](https://m.media-amazon.com/images/I/21av1UAevaL._SL160_.jpg)




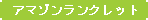
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments