神海に沈む月
千本桜の近くの池に堕ちる蒼雪さんと、ひと目ぼれジェネラルの話。
彼に一番最初に出会ったのは確か入学式の後。
堅苦しい式から逃げ出したかったというのと、答辞という生徒会執行部にとって大きな仕事が終わったという解放感から、ふらふらと、ここに来ていた。
何かあるとすぐここに来てしまう。
大きな大きな千本桜。
この木を見ていると、どんな小さなことでも
霞んでしまうような気がするから不思議だ。
「…あれ」
近づこうとしてふと立ち止まる。
どうやら先客がいるらしかった。
「…!」
桜の木の下に佇むその人は。
蒼く美しく…そう、言うなれば。
「…桜の精…?」
非現実なものは信じていなかった。
そう、思っていた生徒会執行部が思わず溢してしまうほどに、その人は美しかったのである。
「…なんだ、貴様は」
声が届いたのだろう。
その人がこちらを向いた。
「うわっ、わ、すみません!」
思っていたよりも精悍な顔立ちに生徒会執行部は慌てて謝る。
「謝罪はいい。何者かと聞いている」
「せ、生徒会執行部と申します」
有無を言わせない様なそれに生徒会執行部は恐らく彼が望む答えを口にした。
「生徒会執行部…ああ」
少し考える様に彼が下を向き、生徒会執行部の名を紡ぐ。
それからすぐ何かを思い出したようにすい、とこちらを見つめた。
「今日の式で答辞を読んでいた」
「は、はい」
「そうか」
彼が微笑む。
春の風と共に彼の雪模様が付いた蒼い振袖がはためいた。
「貴方は、一体…?」
「…そうだな、特別に教えてやろう」
子どもっぽい笑みを浮かべた青年が口を開く。
「蒼雪」
「え?」
「これが、俺の名だ」
軽く彼が言ったその名は、生徒会執行部もよく知るそれだった。
この帝都を護る軍人将校。
誰もが知る、吹雪の家紋を染め込んだ零ノ桜…蒼雪。
生徒会執行部には手の届かない人だと思っていた。
遠くから見つめていれば十分だ…そう思っていたのに。
「どうした?」
綺麗な笑みを浮かべた蒼雪がこんなに近くにいる。
頭が真っ白になった。
「蒼雪、さん」
「うん?」
蒼雪が首を傾げる。
「どうした、生徒会執行部」
笑う彼は抱いていた印象とは違い、随分柔らかかった。
酒でも入っているのだろうか。
見た限りでは顔は紅く無さそうだけれど。
「…桜、好きなんですか」
「どちらかといえば雪の方が好みだ」
漸く絞り出した質問に、くすりと蒼雪が笑う。
おかしな人だと思った。
見事な桜の木の下で、既に消えてしまった雪に想いを馳せるなんて。
冷たいだけの雪のどこが良いのだろう。
「雪はいいぞ。私のー…」
言いかけた蒼雪の言葉を遮るように、さあ、と風が吹く。
桜が散る音に紛れ、その声は生徒会執行部には届かなかった。
なんと言ったか、と聞き返す隙もない。
ただ、彼がそのまま桜に連れ去られてしまうような気がして。
生徒会執行部はその風に負けぬよう声を張りあげた。
「僕は!桜が好きです!」
「…ほう?」
先程は邪魔をした風が、今度は生徒会執行部の言葉をきちんと蒼雪に伝えたらしい。
おかしそうに蒼雪が笑った。
ただ、馬鹿にするようなそれではないことに、生徒会執行部は安堵する。
「では問うが貴様は何故桜が好きだと言う?」
「え…?」
「明確な理由があるのだろう?」
こてりと首を傾げる様は子どものそれだった。
「…僕、は…命短くとも、美しく咲いて潔く散る桜に武士道を感じるんです」
「武士道、か」
なるほど、と蒼雪は頷く。
「確かにそうだな。しかし、花を咲かすには長い鍛錬が必要だろう」
微笑んで蒼雪が言った。
猫の長い尾っぽのように軍服の袖を舞わせて、蒼雪が紡ぐ。
「桜にとっての鍛錬が、雪だ」
「…はあ」
「少し分かりにくいか」
生徒会執行部の様子にくすりと蒼雪が笑った。
「例えばな、雪を俺と、桜を民だとするだろう。桜は雪が嫌いだ。例え冬の寒さから護ってやっているとしても、桜は冷たいだけの雪を好きだとは言わんのだよ」
「ええと」
余計に分からない。
今度は蒼雪も何も言わなかった。
「難しいことは分からないのですが…」
困ってそう言えば、くすくすと彼が笑う。
「辞書をひけ」
機嫌良さそうに笑いながら蒼雪が言った。
悔しいな、と思う。
雪が好きな桜もいるかもしれないのに。
…この、自分の様に。
「…さて、そろそろ行くか」
「えっ」
くるりと踵を返しかけた彼に、思わず声が出た。
「何だ?俺に仕事をサボれと?」
くすりと意地悪く蒼雪が笑う。
確かに、この街を護る彼を、これ以上ここには留めさせるわけにはいかなかった。
それでも、生徒会執行部にとっては、願ってもいない出来事で。
この夢のような時間が終ってしまう。
雪が解けてしまう様に。
桜が散ってしまう様に。
それを…嫌だと、思った。
「そ…!」
「?」
思わず声をかけてしまう。
彼が不思議そうな表情で振り返った。
「蒼雪さん、は」
やっと絞り出した声は震えてはいない、と思う。
何を言おうか、と考える間もなく、言葉が口をついた。
「思いを寄せる方はいますか?!」
「…は?」
驚いた様に目を丸くする彼に漸くしまった、と思う。
だが、出てしまった言葉は如何あっても、取り消すことが出来なかった。
「…そう、だな。…思いを寄せる…そういうのはいない」
「…え?」
碧い眼を伏せて言う蒼雪に、今度は生徒会執行部が驚く。
「護ると、誓ったものは大勢いる。家族、仲間、街の民…しかし、思いを寄せるなどというのは、ないな」
そう言う蒼雪の頭に桜の花弁が落ちた。
彼も無視をすればいいのに律儀に答える辺り、まだ此処にいたいのだろうか。
そんな事を思ってしまい、生徒会執行部は自嘲した。
まさか、そんなことはあり得ない。
これはただ戯れに答えてくれるだけなのだ、と。
「何故、です?」
「俺は軍人だ」
問いかける生徒会執行部に彼が微笑む。
それは雪のように柔らかく、どこか冷たさを
含んだ笑みで。
「軍人に愛だの恋だの必要があると?」
蒼い軍服をひらり舞わせて蒼雪は問うた。
「…。…僕はそう思います」
それが哀しくて、生徒会執行部は口を開く。
「何?」
「軍人だからと言って恋をしてはいけない理由にはなりません。愛を欲してはならない言い訳にはなりません。真に平和を望む軍人であるなら、誰かを愛するという事を罪だとは言わないはずです」
まっすぐに蒼雪を見てそう言った。
ぽかんとそれを見ていた彼がふっと笑う。
それを見、我に返った。
「も、申し訳ありません!将校様に無礼を!」
勢いよく頭を下げると、上からくすくすと笑い声が降ってくる。
「今更気にするな」
「し、しかし」
「面白い漢だな、生徒会執行部は」
そんな言葉に恐る恐る顔を上げれば楽し気に蒼雪が笑っていた。
許してくれるつもりだろうか。
「では、お前に愛を貰おうか」
くす、と彼が妖艶に微笑む。
呼び方が貴様からお前になっていると気付く間もなく、蒼雪に手を引っ張られた。
「え、え?!」
突然の事に生徒会執行部は慌てる。
あれは己が思う意見を述べただけだ。
自分がどうこうすると言ったつもりはない。
しかし、そんな生徒会執行部の様子を気にすることなく、手を引っ張って歩く蒼雪はどことなく楽しそうだ。
子どものようだな、と思う。
「あの、愛とは…」
「後で辞書をひけ。今は黙ってついて来い」
「は、はあ」
有無を言わせないそれに生徒会執行部はただ頷いた。
恐らく教えてくれるつもりはないのだろう。
雪の様に冷たい表情を見せたかと思えば、桜の如く柔らかい顔も見せる蒼雪に、生徒会執行部は小さく笑った。
美しいだけの、遠くで見つめていた軍人将校の様相がガラガラと音を立てて崩れていく。
「…ここだ」
「…え…?!」
連れてこられた先、蒼雪が指さすそれに思わず声を上げた。
有り得ない、こんなこと。
「…一体、何故」
「不思議だろう?」
楽しそうに蒼雪が笑う。
そこにあったのは白い雪が残る中に咲き誇る桃色の花弁をつけた大きな木だった。
幻想的な雰囲気のそれは見る者を圧倒させる。
それは生徒会執行部も例外ではなかった。
「…ここは、秘密の場所なんだ」
「え?」
「家族も知らない。俺だけが知っている場所」
泣き笑いのような表情で蒼雪が言う。
家族も知らない…完璧な私的空間。
何故そこに自分を、と見上げると、彼は静かに笑って見せた。
「…愛を、教えてくれるのだろう?」
「あ…」
「俺は、軍人に愛などいらない。…そう思うのは変わらん。しかし、俺自身を愛するなとは言わん」
ふわりと彼が笑う。
「この雪の様に、桜色に染めてくれるだろうか」
意外と子どもっぽい彼が。
まるで猫のような彼が。
桜の花弁のように思いをひらひらと舞わせる。
まるで春に降る雪の如く。
「蒼雪さんは僕の色に染まってくれるのですか」
神聖なそこで、生徒会執行部は囁いた。
雪の如く静かな愛を。
「それはお前次第だろう」
「…意地悪なんですね」
「俺は冷酷な指導官だと皆から言われるからな」
顔を見合わせて二人で笑う。
穏やかな時間が流れた。
嗚呼、何故彼は軍人なのだろう。
何故自分は一民なのだろう。
彼を…哀しいまでに美しいこの人を護る事が出来れば。
…そうすれば、この人はもっと美しい笑みを
見せてくれるのだろうか。
今はただ、猫の気まぐれのように、甘えているだけかもしれない。
ただの戯れかもしれない。
彼が今日この地に来たように。
それでも構わなかった。
手を伸ばしても届かなかった蒼雪がこんなに近くにいる。
愛していいと言ってくれている。
それだけで十分だ。
だから、今度は。
「蒼雪さん」
「なんだ、生徒会執行部」
偶然がなければ出会わなかった…この気高く強い、この人を。
自分は護るとはまだ言えないけれど。
(彼が許してくれた二人だけの地、これだけは…護って見せよう)
どうかどうか。
…誰かを護るために自分を犠牲にする美しい猫にも愛と言う名の桜が舞い落ちます様に、と
生徒会執行部は、普段は欠片も信じていない神に望みを紡いだ。
「またいずれ、桜の木の下で」
「…そうだな。覚えてはおいてやろう」
(終)

![バス&ボディワークス A THOUSAND WISHES アサウザンドウイッシイズ [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41fVUFnRbOL._SL160_.jpg)


![Boin: Lecture One and Two 2 DVD Set [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/51B9wuq5jsL._SL160_.jpg)
![羞恥温泉旅行 秘湯悦楽堕ち 阿部栞菜 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61UIySn8VIL._SL160_.jpg)
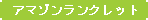
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments