彰冬
ふ、と冬弥は窓の外、星が輝く空を見上げた。
こんな夜はあの時の事を思い出す。
…彼が、自分を連れ出してくれた…あの夜を。
「あら、また空を見ているの?」
「…ルカ、さん」
くす、と笑うのは冬弥の教育係を勤めた巡音ルカだ。
メイド長でもある彼女は仕事に関してはストイックだが、それ意外には優しいのである。
黒と白のエプロンドレスを閃かせ、ルカは笑んだ。
「ご主人様が帰ってきたら一緒に飲むと良いわ」
「…ありがとうございます」
「ふふ、気にしないで」
渡されたティーポットをテーブルに置き、礼を言えばルカは綺麗に笑みを浮かべて部屋を出る。
冬弥も僅かに笑みを浮かべ、また窓から空を見上げた。
「…彰人」
小さく呟き、そんなすぐには帰ってこないか、と仕事に戻ろうとした時である。
「…呼んだか?冬弥」
ぶわりと風が吹き、白のマントがはためいた。
舞い上がる自身の燕尾服を抑え、見上げたその先に居たのは。
「…彰人!?」
不敵な笑みを浮かべ、仕事から帰った…巷で噂の大怪盗、冬弥の主人でもある彰人…であった。
「…随分早かったんだな」
「まあな。やることもいつもと変わんねーし」
「…それは、そうだが」
シルクハットを脇に置いて伸びをする彰人に冬弥は小さく息を吐く。
彰人の執事である冬弥だが、この口調が許されているのはある理由があった。
…それは。
「お前を『盗んだ』あの時に比べりゃどんな仕事も遥かにマシだっての」
ニッと彰人が笑う。
そう、冬弥は盗まれたのだ。
他ならぬ彰人の手によって。
幼い頃から、クラシック界次世代の宝物、と称されてきた冬弥であったが、それが窮屈で仕方がなかったのだ。
そんな折、まだ見習いだった彰人に見つかり、盗んでもらった、のである。
世間はたちまち大騒ぎになったが、それでも今尚彰人の執事として冬弥が暮らしていられるのは奇跡に近かった。
「冬弥、オレの執事。…お前は一生オレのものだ。そうだろ?」
「ああ、勿論。俺の人生の全てはお前のものだ…ご主人様」
風が吹く。
宝物である冬弥の柔らかい笑みは、夜空のカーテンに阻まれた。
(その宝は、奪った怪盗、ただ一人だけのもの!)
「今日は来てくれてありがとう!」
センターであるカイトが笑顔で手を振る。
きゃあ!と女子が黄色い声を上げた。
…これに意味があるのだろうか、なんて考えるのも馬鹿馬鹿しくなってやめる。
クラシックを辞めたくて、父親に反抗したくて応募した書類選考にあれよあれよと通ってしまったアイドル活動は、冬弥にとっては向いていなかったらしかった。
動機が不純すぎる、と小さく息を吐いて、冬弥は着せられた衣装をつまみ上げる。
「…近未来だって、変わってるよねぇ」
「…カイト、さん」
優しい笑顔で話しかけてくるカイトは、舞台上と態度が変わらない、優しい人だ。
この人がいるから、辞めてはいけないと、この場に留まり続けている。
「ね、冬弥くんは知ってる?この衣装、どこぞの怪盗が狙っているらしいよ?何でも、世界中の金庫全てを開けてしまえるのだとか」
「…本当、ですか?」
「さあ?でももし本当なら夢があるよね」
首を傾げる冬弥に、カイトが笑い、楽屋に帰っていった。
和ませてくれたのだろうか、と少し笑みを浮かべ、冬弥も楽屋に戻ろうと足を踏み出した…その時。
ぶわりと、風が吹く。
思わず顔を腕で庇い、風がおさまるのを待った。
「…?」
なんだろう、と恐る恐る目を開き、顔を上げる。
演出でも見たことがない、それ。
おさまった風の中、一人の男が立っていた。
白いシルクハットと同色の衣装、夜空の色と同じマントをはためかせた…オレンジ髪の男。
変わった出で立ちなのに目が離せない。
「…お前、ステージで歌ってたやつ?」
「え?あ、あぁ。そう…だが」
話しかけてきた男にようやっとそう答えればふぅん、と言った。
そうして。
「…お前、オレと来ねぇ?」
「…え?」
手を差し出す男に、きょとんとする。
何を言っているのだろう、この男は。
「お前さ、歌が好きな割にこの業界は苦手だろ」
「…!」
男の言葉に目を見開く。
…事実でしか、なかったから。
「オレと来れば夢を魅せてやるぜ」
「…夢を…?」
「あぁ」
強く頷く男に冬弥はおずおずと手を乗せた。
ぐっとそれを引かれ、腕の中に収まる。
「オレは東雲彰人。一応怪盗やってる。お前は?」
「…冬弥。青柳冬弥。…俺を、連れ去ってくれ」
「仰せのままに」
冬弥のそれに男…彰人が笑った。
トン、と跳び上がり、体が浮く。
目をぎゅっと瞑る冬弥に、大丈夫、という声が響いた。
その声に身を任せる。
何故だか大丈夫だと…思ったから。
その日、世界の宝である一人のアイドルが姿を…消した。
「…っていうのはどうかと思うんだけど…」
「そっちも良いなぁ!迷うよねー…あ、彰人くん!冬弥くん!」
「…なんの話してんだ、オメーらは…」
ぱや!と嬉しそうにリンが笑う。
その声に嫌そうな顔をしたのはレンだ。
嫌なのはこっちなのだが、と思いつつ彰人はレンに軽い手刀を振り下ろす。
「~っ!もうっ!なんでオレだけ?!」
「嫌なら止めとけ」
「…で、何の話を?」
涙目で反論するレンにいけしゃあしゃあと言う彰人を見ながら、冬弥が首を傾げた。
あのねぇ!と楽しそうに説明しだすのはリンである。
「こはねちゃんの、学校のお友だちが遊園地でショーをやってるんだって!それで、台本を考えるのが大変そうだったから皆でアイディアを出してきたんだよって言ってたの!」
「んで、リンが楽しそうっていうからさ?オレも脚本とかそういうの、興味あったし!」
「…だからってオレらで考えんなっつー…」
説明する彼らに向かって呆れたような表情をする彰人に、冬弥がくすくすと笑った。
「ねぇねぇ!冬弥くんはどっちが良い?!」
「…俺か?」
「うん!あたしの怪盗とアイドルか!」
「オレの、怪盗と執事か!」
わくわくとリンとレンが聞く。
オレの意見は、だとか、なんでオレが怪盗なんだ、とかツッコミどころは山程あったが言葉にする前に冬弥が手を握ってきた。
「冬弥?」
「…俺は、この…俺の隣にいてくれる彰人が一番良いな、と…思う」
にこ、とリンに向かって微笑む冬弥。
うわぁ!と目を輝かすリンと、「…冬弥って天然無自覚?」と彰人に囁いてくるレン。
それに視線で返事をし、まだ何か聞き出そうにするリンと、何なに?と様子を見に来たミクとMEIKOから逃げるべく、握られた冬弥の手をぐっと引いた。
そして。
「…あー!逃げた!」
「うるっせ!オメーらに構ってる暇はねーの!…走るぞ、冬弥!」
「え、あ、彰人!!」
焦る冬弥を引っ張って彰人は走る。
まるで、宝物を奪う怪盗のように。
風をきる。
セカイを駆けて。
二人ならば何処までも行ける気がした。




![Testosterone Factor [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41A4F7dVzRL._SL160_.jpg)

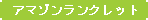
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments