機械仕掛けの神様なんてクソくらえ(改)
…かんっぜんに選曲ミスった。
そう、ため息を吐いたのは彰人だった。
「…大丈夫か?彰人」
心配そうに覗き込む相棒…だけではないが…の、冬弥に突っ伏したまま手を振る。
一応大丈夫、というのが伝わったのか彼はホッとした表情を、した。
「飲み物、いるか?」
「…んじゃあブラック以外で」
「…分かった」
小さく笑った冬弥がパタパタとスタジオから出る。
それを見送りながら彰人は自分が持ってきたはずの楽譜を手に取った。
Anti the EuphoriaHOLiC
そう銘打たれた楽曲は、とにかく速いし曲調もコロコロ変わるしで歌うのがかなり難しいそれだった。
普段やらないジャンルを、と探してきたはいいが完全に間違ったな、と再び項垂れる。
ツインボーカルだし、これが歌いこなせればパフォーマンスも映えるだろう、なんて安易に思ったのが間違いだったのだ。
これは人間が歌えるものではない。
バーチャルシンガーたちだからこそ映える歌なのだろう。
…ちなみに前身であるAnti the ∞HOLiCはカラオケに入っているようだ、どうかしている、と汗を拭った。
(つか、作者は何を思ってこの曲を作ったんだ?)
ため息を吐きながら彰人はそう思う。
Фはセカイとは読まねぇだろ、普通…、と独りごちていれば、またパタパタと足音が聞こえてきた。
「…これで良いか?」
「…ん、サンキュ」
缶ジュースを持って戻ってきた冬弥からそれを受け取る。
彰人の好きなものを熟知しているのは流石相棒、といったところだろうか。
缶を煽れば甘く爽やかな味が喉を潤していく。
「冬弥は大丈夫か?」
「…俺、か?俺はまあ…」
「無茶すんなよ」
困った顔の冬弥にそう声をかけた。
彼は感情を表情に出さないからである。
まあそこが冬弥らしいといえばらしいのだが。
それに、前より分かりやすくなった。
特に、楽しい、という感情はより伝わってくるようになったのだ。
彰人はそれを嬉しい、と思う。
父親を吹っ切って、クラシックを受け入れて、冬弥はより豊かな歌声を響かせるようになった。
彰人と、それからこはねや杏と共に、伝説を超える、その為に。
それを、嬉しいと呼ばずに何というだろうか。
「彰人が選んだ曲だろう?…難しくても、やり遂げてみせるさ」
冬弥が小さく笑う。
「…オレは、こいつのこういうトコが好きなんだよなぁ…」
その言葉に彰人はそっと独りごちた。
彰人を、真っ直ぐに信じてくれる。
なんだかんだ言いながら着いてきてくれる。
だから自分ももっと高みへ行けるのだ。
あの、喧嘩で、再確認した。
彰人は…彼と、冬弥と歩いていきたい、と。
「辿るべき道標(ひかり)はその胸に――、か」
「彰人?」
きょとんとした顔で冬弥がこちらを向く。
何でもねぇよ、と彰人は答えて立ち上がった。
よく分からない歌詞の羅列で、唯一共感したそれ。
辿るべき目標(ゆめ)は、彰人の…彰人たちだけのもの。
自分たちは自分たちだ。
決めるのは他の誰かなんかではなかった。
カミサマなんていらない。
デクス・エクス・マキナなんてもっとごめんだ。
真実に興味はないし、そも、自分たちが掴んでいるものこそが真実だと、彰人は信じていた。
だが、不幸と思ったって決まってしまった結末を捻じ曲げることは絶対にしない。
へや(過去)の飛び出したマリー(人類)のように、夢を、伝説を掴むために進むのだ。
まっすぐ、希望だけを胸にして。
彰人たちの野望はまだ、始まったばかりなのだから。
絶望なんてそこにはない。
苦しいことがあったって、頼ってほしいと手を差し伸べてくれる彼がいる。
それだけで充分だ。
…ただ、歌と冬弥がいれば…それでいい、と。
「練習再開すっぞ!!」
「…ああ」
呼び掛ければ、ふわり、と冬弥が笑う。
中々見れない、柔らかなそれで。
その笑みを見て、彰人も強気に笑った。
難しい歌だってなんだって、冬弥がいるならやってやる。
…冬弥の笑顔のためなら、オレは…バッドエンドも書き換えてやるよ。
「ぜってぇ嫌だ。誰がんなふりっふりの服着るかよ、司センパイじゃあるまいし!」
「…フリルと言っても腰のところだけだろう。きちんとした男性用衣装だぞ?大体司先輩の衣装はステージ衣装だからで…」
「彰人はさあ、ワガママだと思うなあ」
「…レン」
「ここのレンを見てよ、まともな衣装が二割しかない」
「…。…オレが悪かった」
![[comprout] FTWフォーグ セット](https://m.media-amazon.com/images/I/512OWHVTNiL._SL160_.jpg)

![バス&ボディワークス A THOUSAND WISHES アサウザンドウイッシイズ [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41fVUFnRbOL._SL160_.jpg)

![羞恥温泉旅行 秘湯悦楽堕ち 阿部栞菜 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61UIySn8VIL._SL160_.jpg)
![カーディオキック・ダイエット [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/511kxcFeKfL._SL160_.jpg)
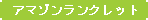
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments