花言葉に思いを寄せて(へし燭・安清・くにちょぎ)
<蒲公英>
太陽のようにきらきらと輝く金の髪。
自分とは違うそれをもっと見ていたいと思った。
戦場で揺れるそれを。
写しである彼の髪は風に乗って己の目を引いた。
ややあって気付く。
それは確かに恋だった。
「偽物くんなんて嫌いだ!いいか、俺の傍に近付くな。顔も見たくない!!」
吐き捨てるように言って部屋を出る。
何か言っている声が聞こえたが聞きもしなかった。
自室に入り…扉を閉めることもなくずるずると座り込む。
…まただ。
はあ、と溜め息を吐く。
何度目だろう。
自分の写しである彼にこんなことを言ってしまうのは。
彼、山姥切国広は優しかった。
本丸の事を何も知らない自分に色々と教えてくれた、ただそれだけだったのに。
山姥切国広は博愛主義者だ。
誰にでも優しいと気が付いてしまえば絶望も早く。
国広の博愛は自分にだけ向けられているものだと勘違いしていた。
愚かだと思う。
博愛が自分だけのものではないと知ってなお、それが自分だけに向けて欲しいと身勝手に国広を傷つける。
最低だ。
「…長義くん?」
「…祖…じゃなかった、燭台切さん」
開いた扉の隙間からきょとんと覗き込んでいたのは長船の祖である燭台切光忠だ。
祖、というと複雑そうな顔をするからあまり呼ばないようにしているが。
「どうかしたの、長義くん」
「…えっと」
「話くらいなら聞くけど」
柔らかく微笑む彼にどこか安心した。
「そうだ、おやつもあるよ」
「…いただこうかな」
それに笑みを返そうとして…失敗する。
「…俺は、偽物くんに酷い事をしているんだ」
「…」
「分かっては…いるんだけど。あいつが他に笑いかけるから。どうしようもなくて…」
「…。…長義くん」
吐露する長義に光忠が笑んだ。
「嫌だと言ってしまえばどうかな」
「そんな無様なこと言えないだろう。そんな、醜い…」
「それが醜いかどうかはきっと、国広くんが決めてくれる。彼はそんなことで困るような弱い刀じゃないよ」
なんたって君の写しなんだから、と笑う光忠にはっとした。
「…そうか、な」
「きっとそうだよ」
自信無げに問いかければ、光忠は、はっきりとそう頷く。
優しい彼は自分の想いを、どうするだろうか。
本歌が言うなら、と受け入れるだろうか。
今まで散々酷い事をした相手にと断るだろうか。
「…見て、蒲公英だ」
光忠の言葉にそちらを見やる。
なぜか残っていたのだろう、綿毛にもならない蒲公英が一輪、咲いていた。
揺らめく花は国広の髪の色に似ている。
自分の視線を奪った…その色に。
恋心を奪った、その色に。
真心の愛、と言葉がある蒲公英はまるで国広のようだと思った。
小さな太陽のようだと。
そんな彼の傍にいてもいいのだろうか。
綿毛のように…離れなくてはいけないのではないだろうか。
「考えすぎだよ、長義くんはさ」
「…」
「もっと軽く考えてみてはどうだろう?君の所為で可笑しくなったんだから、責任を取れ!くらいにさ」
「…そう、軽く言えればいいのだけど…ね」
光忠にしてはらしくない軽口に長義も可笑しくなって笑った。
確かに、そうかもしれない。
偽物くんに悩まされてるだけなんて、そんなことがあっていいだろうか。
「有難う。少し元気が出たよ」
「それは良かった」
柔らかく光忠が笑う。
「燭台切さんの淹れた珈琲が飲みたいんだけどな」
「勿論。仰せのままに」
くすくすと笑う、二人のそれは…風に乗って消えた。
彼の事は好きだ。
それはきっと認めなければならない事実。
ならば受け入れよう。
蒲公英が小さく風に揺れる。
その方向は…別離かはたしてそれとも。
<黄色い鬱金香>
彼の明るさは、己の自慢でもあった。
自分は決して明るくないと分かっていたから。
笑顔を見せる彼は川の下の子、なんて呼ばれた自分には眩しいもので。
見ていたいのに見たくなかった。
矛盾している、と思う。
この思いは、と考え、はたと辿り着く。
それは確かに恋だった。
「どうかしたのかな」
「…長義」
「君がそんな顔をするなんて珍しいじゃないか」
柔らかい声に振り仰げばきょとんとした山姥切長義が清光を見下ろしていた。
良ければ話くらい聞くけど、なんて隣に座りながら長義が笑う。
「…長義はさ、優しいよねー」
「褒められているのかな、それは」
清光のそれにくすくすと綺麗に笑う長義。
本丸に顕現したのは最近の筈なのに、随分と前から一緒にいるかのようだ。
柔らかく笑う彼の隣は、酷く心地良い。
「で?悩める清光君はその訳を聞かせてくれるのかな」
こてりと首を傾げる彼はやっぱり綺麗で。
なるほど、彼もまた長船の刀なんだなと思った。
「大した話じゃないよ」
「こうやって悩んでいるんだから、それは君にとって大した話だと思ったのだけど?」
小さく笑った長義は懐から何かを取り出す。
「…これ」
「貰い物。一緒に食べてくれると嬉しいな」
「…。ありがと」
微笑む長義に清光は素直に礼を言った。
差し出されたそれは清光の好きな菓子である。
気遣いも完璧な彼に思わずはっぁあ、と大きな溜め息を吐き出した。
「俺、あんたみたいな人を好きになれば良かった」
「…どういう意味だい?それ」
きょとん、と長義が目を瞬かせる。
こうなれば自棄だと清光はごろんとその場に寝そべった。
「俺さ、好きな人がいるんだ。相手は何百年も相方だった刀」
「…それって」
「そ、大和守安定」
驚きに鴨頭草の瞳を見開く長義に笑いかける。
ずっとずうっと、好きだった。
昔からの相棒である…彼の事が。
親愛として好きなだけではない。
愛していた。
明るくて、誰からも好かれる彼の事を、心底愛していたのである。
「…大和守に…その思いは、伝えるの?」
「まさか。…この思いは、折れるまで永遠に俺だけのものだよ」
清光は小さく笑う。
自覚した恋心は刀である自分たちには不要なものだった。
それに安定には恋なんて自覚させて折れてしまった方が困る。
望みのない恋、報われることのない…恋。
「俺は、沖田の刀。大和守安定の相棒。…それだけで十分」
「…そう。清光君がそれでいいなら、俺は何も言わない。周りが介入すべきでないと思うし」
「…ありがと、長義」
「どういたしまして」
長義が笑い…ふと何かに気付いたように指を差す。
「…随分季節外れの花が咲いているね?」
「…え、ああ」
言われて目を向けた先にあったのは黄色い鬱金香であった。
どうせ主が景趣を春から変えていないのだろう。
そよそよと風に揺れる黄色い花弁は季節外れなのにどこか美しい。
「赤や白は良く見るけど、黄色の鬱金香というのは珍しいね」
「そう?黄緑や紫よりは良く見る色だと思うけど」
「ん…俺は好きだけれどね、この色」
にこにこと長義が笑った。
明るい色は、彼の要素がないのにどこか安定を思わせる。
「…そーね、俺も好き」
清光の返答にまた長義も笑んだ。
「そうやって軽く言ってしまえば良いのに」
「…。…軽く言えたら、いーんだけどね」
くすり、と清光が肩を揺らす。
「この話はもうおしまい!…ほら、行くよ!」
ぱっと起き上がって長義の手を引いた。
「え、ちょ、ちょっと!!」
慌てる長義をいいから!と立ち上がらせ駆け出す。
ふわり、と鬱金香の黄色い花弁が、揺れた。
彼の事は好きだった。
愛していた。
けれどそれを伝えることは…きっと、ないだろう。
だって、永遠に秘密の恋であるから。
これは報われない…恋なのだから。
<紫金牛>
幼い頃から…まだ自分が実態を持たない頃から気付いていたはずだった。
たなびく榛色の髪が短くなってしまっても。
己の心は藤紫の瞳に囚われたままだった。
尊敬などと言う美しいものではない。
手を伸ばしたそれがどんなにどろどろしたものか、等。
幼少より隠してきた思いはずっと知っている。
それは確かに恋だった。
「燭台切さんっ」
「…清光くん?」
明るく声をかけてきたのは加州清光だ。
初期刀である彼とはなかなか古い付き合いでもある。
「どーしたのー?元気ないじゃん」
からりと笑う清光に、適わないな、と笑った。
「俺で良ければ話聞くよ?…いつもお世話になってるし」
「僕は別に何も…」
「いいから!」
口ごもれば、そう押し切られて座らされる。
ほら、と出されたのは光忠が好きな菓子だ。
「たまにはゆっくりしなよー?…燭台切さん、いつも忙しいんだし」
「…清光くんが言うのかい?それ」
元気な清光にくすくすと光忠が笑う。
初期刀の彼が主から色々と任されているのは知っていた。
「俺の話はいーのっ。で?何悩んでるのさ」
「…」
清光の無邪気なそれに、光忠ははあ…、と溜め息を吐き出す。
「嫌なら言わなくてもいーけど」
「…嫌じゃ、なくて」
「…。…なあ、あの花、何?」
もごもごと言う光忠に清光は深く詮索しない事を決めたのだろう、ふと庭の方を指さした。
見たその先にあったのは。
「…あれは紫金牛だね。夏に梔子色の花を咲かせて、冬には赤い実をつけるよ」
「へえ。初めて見た」
にこにこと清光が言う。
「…聞いてくれるかい?清光くん」
「ん。なーに?」
小さく告げる光忠に清光がにこりと笑った。
「僕ね。長谷部くんが…好きなんだ。紫金牛の花言葉のように」
「…」
光忠のそれに清光は黙る。
紫金牛、花言葉は【明日の幸福】。
彼がいるから明日もきっと幸福だろうと思うのに。
それなのに、なんと無様な事だろう。
彼の隣に他の誰かがいるという事実が…酷く辛い。
…へし切長谷部は主の刀だ。
自分も刀だし、それについて何の疑問もない筈だったのに。
彼が他に笑いかけることがこんなに辛いとは思わなかった。
それが親愛である以上の物はないと…知っているはずなのに。
自分だけを見て、幸福を与えるのは自分だけにしてほしいと思っている。
「…燭台切さんも意外と拗らせると酷いよね」
「…意外とって…」
その声に恨めしくなって隣の清光を見やった。
彼は思った以上にいたずらっ子の表情をしていてほんの少し驚く。
「燭台切さんはさー、色々我慢し過ぎだと思うよ?」
「ええ…」
ぶらぶらと清光が足をぶらつかせながらそう言った。
「へし切なんて超鈍感なんだから。言うもん言っていかないと伝わらないと俺は思うけど」
「…そう、かな」
「そうだってー」
からからと清光が笑う。
「案外直接言っちゃった方が、良い事もあるよ」
「清光くんが言うならそうなのかもね?」
「何、それー」
結構本気なのに!とぶすくれる彼の頭を撫でた。
きっと彼は知っている。
光忠の…長谷部への汚い思いも、何もかも。
だからこそ軽くこういうのだ。
その軽口が今は酷く心地良い。
「ありがとう、清光くん」
「えへへー。お礼は、俺の好きなおかずでいーよ?」
「ふふ。善処はしようかな?」
にこりと二人で笑い合った。
「さて。じゃあ手伝ってくれるかい?」
「しょーがないなー」
立ち上がり、二人で部屋から出る。
庭の紫金牛がふわりと、揺れた。
彼の事は好きだ。
その思いを嘘にすることは出来ない。
不穏と共に、思いを消すことは…出来ないのだから。
だからこそ、大切にしようと思う。
彼に対する、この思いを。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ふわりと、風が吹く。
「かっわいいんだから」
くすと小さく笑ったのは安定だった。
「そう思いません?」
笑いかける相手は酷く苦虫を噛み潰した表情をしている…長谷部だ。
「可愛いのか?あれは」
「可愛いでしょう、僕の清光」
「それなら光忠の方が…余程可愛らしいと思うが」
安定のそれに長谷部はしれっと返す。
「長谷部さんもなかなかあれですよね」
「お前が言うのか、それを」
くすくすと二人で嗤った。
…と。
「うちの本歌も可愛らしいだろう?」
「…山姥切」
間に入ってきたのは国広である。
「あれは…可愛い…のかな…」
「可愛いだろう。俺の本歌は」
小さく国広が嗤った。
「歪んでいるな」
「貴様に言われたくはないんだが?」
長谷部が言う。
そう、歪んでいる。
これは綺麗な恋などではなかった。
美しい愛などでもない。
ただの、汚く歪んだ独占欲だ。
彼らは、恋を…独占欲で潰された。
それを知る事はもう、ないのだろう。
かわいそうな…彼らの結末は。
黄色の花弁が揺れる。
その花の名は…。
(終)
![羞恥温泉旅行 秘湯悦楽堕ち 阿部栞菜 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61UIySn8VIL._SL160_.jpg)
![秘湯めぐり美女 混浴温泉に単独で来た女性たちが睡眠薬入りの地酒を飲まされ昏睡したところを強姦にあっていた事件映像 レッド [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51CTju1IdsL._SL160_.jpg)
![Casper [Blu-Ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41mn0TsXyGL._SL160_.jpg)
![La Couleur Pourpre 1985 + Version 2023 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/516WA6A6FnL._SL160_.jpg)
![Casino [4K Ultra HD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41Bh+1Qg4TL._SL160_.jpg)
![Casino [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41zTTWRvrWL._SL160_.jpg)
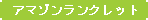
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments