元気ない君に両手いっぱいの(冬弥総愛され)
灰色の空を見て類ははあ、と息を吐く。
白いそれが空気に舞い、消えた。
高い背を縮こませて通学路を歩いていたが…ふと目の前に見たことのあるツートンカラーを見つける。
確か、彼は。
「…やあ、おはよう。青柳冬弥くん?」
「…。…おはよう、御座います。…神代先輩」
類を認めた彼…冬弥が小さく会釈をした。
礼儀正しい子だな、と思う。
あの、司を慕い尊敬する後輩、だとは未だに思えなかった。
やはり反面教師だろうか。
…それよりも。
「…あの?」
「ん?ああ、すまない。君は冬、と名にあるだけあって寒さに強いのかと思ってね」
「え…」
驚いた顔で彼がこちらを見る。
冬弥は何故だか防寒具を身に着けていなかったのだ。
こんなにも寒い日なのに。
「…。…強くは、ないです」
小さな声の冬弥が視線を下に落とす。
どうやら朝から何かあったようだ。
表情変化は少ない冬弥だからこそ、小さなこれは手に取るように分かった。
あまり個人に入り込むことはしたくはないが…彼が元気がないのは少し気になる。
ふむ、と考え込んだ類はカバンを探り、衣装用にと持ってきたストールを巻いてやった。
「…え」
「なら、せめてそれを巻いておくと良い。…違反ではないはずだしね」
くす、と笑いそれからいつも持ち歩いているラムネを取り出す。
「あ、あの、ありがとう御座いま…」
「はい、あーん」
おずおずと礼を言おうとする冬弥を遮ってラムネを口に入れた。
驚いた表情で見上げる冬弥が可愛いな、と思う。
「ラムネは苦手だったかな?」
「…いえ」
「なら、もう一つどうぞ。…糖分は、大事だよ?」
白い粒が入ったビンを振りながら言えば彼は灰青の瞳を少し大きくさせた。
何故、と言外に問うから、そうだねぇ、と指を伸ばす。
「いつもピンと伸ばされている背が小さく見えた。それに表情が硬い。今更僕に緊張なんてしないだろう?なら何かあったのかと思ってね。何はなくても糖分摂取は効く、から」
そう説明してやれば、冬弥はややあってふわ、と笑んだ。
思わず類も笑顔になる。
ありがとう御座います、と言う冬弥の声が透き通った朝の通学路に消えた。
寒い、と司は空を見上げた。
昼食は外で食べる!と決めていたが…今日は室内でも良かったろうか。
粗方食べ終わった後で後悔しても仕方ないのだが…と。
「…あれは」
見たことあるシルエットに司は、おぅい!と声をかける。
「冬弥!こっちだ、こっち!」
「…司、先輩」
本を抱えた冬弥が司の声に振り向いた。
綺麗な髪が揺れる。
「昼休みも委員会か?大変だなぁ」
「…はい」
軽い気持ちで言ったが冬弥は力なく笑みを浮かべた。
おや、と思う。
「…もしや、とは思うが…冬弥、お前昼は…?」
「…持ってくるのを忘れてしまって」
「何?!」
冬弥の短い一言に目を見開いた。
「委員会で忙しかったし、丁度良かったんです」
「何が良いものか!ほら、座れ座れ!」
ポンポンと隣を叩く。
成長期の男子高校生が昼抜きは辛かろうに。
はあ、と隣に腰掛けた冬弥に食後にと取っておいたデザートのミニケーキを差し出した。
「…え」
「なんだ、甘味は嫌いか?」
「…いえ。でもそれは司先輩のでは…?」
「遠慮をするな!可愛いオレの後輩が午後中ずっと腹を空かせていると思う方が辛いに決まっているだろう」
何を当たり前なことを、と言えば冬弥は目を見開く。
「…ありがとう、ございます」
「礼は後だ。ほら、口を開けろ、冬弥」
ん、と促すと今度は素直に口を開いた。
彼の小さな口にケーキを入れる。
ほわ、と笑みを僅かに浮かべ、美味しいです、と冬弥が咀嚼しながら言った。
「そうだろう!!後…そうだ、クッキーも入っていたな。これは包んでやるから後で食べると良い」
「え、でも」
もごもごと何かを言いたそうにする冬弥の頭を撫でる。
「まったく、冬弥は。少し甘えてもくれないのか?」
「…!!」
目を見開く冬弥に司はニッと笑ってみせた。
気丈な後輩が、安心できるように。
「確かにオレは冬弥にとって頼りないかもしれないが。たまには先輩ヅラさせてくれ」
「…司、先輩」
「年下が年上に甘えるのは当然の権利だ。そうだろう?」
笑い、くしゃくしゃと彼の髪を撫で回す。
ようやっと柔らかいそれで、はい、と言った。
「…まあ、あれっぽっちの甘味では余計に腹も空こうが…」
「いえ。…司先輩の気持ちが嬉しいので」
「冬弥…!」
綺麗な笑みの冬弥に思わず崇めそうになる。
もう一人の後輩とは雲泥の差だ。
…まあ彼、の場合は冬弥が司に懐いているのが気に食わないのもあるのだろうが。
「よし!自販機に行くぞ、冬弥!せめて飲み物を奢ろう!」
「司先輩、それは…!」
さっさと弁当箱を片付け、冬弥の手を引っ張る。
慌てたような彼に司は笑った。
まったく、冬弥は真面目なのだから!!
「オレの可愛い冬弥に、オレがしてやりたいんだ!…昼の時間は少ない、急ぐぞ、冬弥!!」
「おい、冬弥!帰るぞ!」
彼のクラスのホームルームが終わったと同時に彰人は声をかけた。
クラスメイトは、相も変わらずと気にする様子もない。
ああ、と冬弥が荷物を纏めて出てきたと同時に手を引いた。
「…彰人…?」
「うるせぇ」
不思議そうな彼にムスッとしたまま玄関ホールに向かう。
靴、と短めに指示をして履き替えるのを待った。
グラウンドを突っ切り、校門を出ていつもとは反対の道に進む。
「彰人、どこに…」
「いいから黙って付いて来いっつーんだよ」
不安げな冬弥に、ったく、と彰人はため息を吐いた。
立ち止まったのはよくあるコンビニだ。
「…?また新作のチーズケーキか?」
「違げぇ。…お前、朝からあんま食ってないだろ」
「…!なぜ、それを」
「見りゃ分かる。…なんで我慢してんだか」
驚く冬弥に息を吐き、コンビニに入る。
冬になったからだろう、ホットスナックが並んでいて。
これで良いかと中を見る。
「オレは肉まんにするけど。冬弥は?」
「…俺、は」
振り向くと冬弥は少し困った顔をしていた。
なんだ?と思えば、少しして食べたことないんだ、と告白してくる。
「マジか。…なら尚更食ってみたいもん食えよ」
「…だが」
「練習、保たねぇぞ」
彰人のそれにようやっと冬弥も頷いた。
彼が指差したのは紫芋のコロッケで。
その色味に、2年の変人…何か奇妙なものを作る方…がぼんやりと浮かび、慌てて打ち払う。
レジで肉まんやピザまん、飲み物と共に冬弥の選んだコロッケも注文した。
「…随分買ったな」
先に外で待っていた冬弥が意外そうに言う。
お前のだよ、と言い、隣に座った。
「…多過ぎないか?」
「足りねぇだろ。朝も昼も碌に食ってねぇくせに」
「…!だが」
「うだうだ言ってねーでまずは食えよ」
言い募る冬弥にほら、とコロッケを差し出す。
むう、とした表情のままそれを齧った冬弥のそれが、ぽわりと溶けた。
「美味いか?」
「…ああ」
「そりゃ良かったな」
「お前も食べるか?」
ん、と差し出してくる冬弥に、遠慮しても彼は引かないだろう、と素直に出されたそれを齧る。
「ん、案外いける」
「…そうか」
何故だがその言葉に嬉しそうに頬を緩める冬弥に、変なやつ、と彰人は笑った。
食べ終わった頃を見計らい、ピザまんを差し出す。
今度は素直に受け取り、小さな口で齧りついた冬弥が少し目を丸くさせる。
どうしたのかと思えば中に入っているチーズが切れなかったようで困った顔で見上げてきた。
思わずふは、と笑う。
「…わりぃ」
一頻り笑い、一応謝ってから伸びたチーズを切ってやる。
「…悪い顔していたぞ、彰人」
「そりゃなるだろ」
肩を揺らし、自分用にと買った肉まんを割った。
湯気が冷たい空気に触れ、白に変わる。
半分になったピザまんと交換し、齧りついた。
少し懐かしく感じる味が口いっぱいに広がる。
「…美味しかった。ありがとう、彰人」
「…おお。ちょっとはマシになったな」
礼を言う冬弥の頬に手を伸ばした。
ひやりとした感覚が指先に伝わる。
「冷てぇの」
「今日は寒いからな」
すり、と頬を擦り付けたかと思えば、冬弥はその手を持ってゆっくり微笑んだ。
「だが、代わりに心は暖かいぞ」
「…そーかよ」
無意識か、と脳内でツッコミながら、短く返す。
彼が幸せであればそれで良いか、と思った。
いつだって冬弥には、幸せで…いてほしいのだから。


![Kate & Allie: Seasons 5 & 6 [DVD] [Import]](https://m.media-amazon.com/images/I/51+zKBc8pqL._SL160_.jpg)
![True Nature [DVD] [Import]](https://m.media-amazon.com/images/I/51zDn1bfr8L._SL160_.jpg)


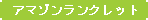
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments