冬弥♀ちゃんをイジメるモブ女子にブチ切れる彼氏ズの話
最初の印象は、キレイな髪で、指の長い女の子だなってことだった。
意外にハスキーな声の彼女は、これまた意外に友だちが多くて。
「…ねぇ、青柳さん。何か探してるの?手伝ってあげても良いけど」
「…。…草薙。…ありがとう、助かる」
「代わりに、読みたい本があって…」
クラスメイトでもある草薙寧々と連立って図書室に行ったりだとか。
「お待たせ、冬弥!!…あれ?なんか寝不足?元気ないけど、大丈夫?」
「…。…いや、新しく買ったミステリー小説が良かったんだ。…白石も読んでみるか?」
「えー、私に読めるかなぁ」
風紀委員の白石杏と笑いあっていたりだとか。
「やっほー!…って、あー!またそんなちょっとしか食べてない!弟くんに言いつけてやるんだから!」
「っ!それだけはやめてくれないか?暁山」
「もー、ならちゃんと食べれば良いのにさぁ」
あの暁山瑞希と昼食を共にしていたりだとか。
どことなくぼんやりしているのに、彼女には隙がなかった。
…いや、多分、これは、皆に守られている。
何故分かるか、って?
…そんなの、見てればわかる。
女の子だけじゃない。
例えば…ほら。
「おい、冬弥ぁ!さっさと帰るぞ!」
「冬弥!たまにはオレが、家まで送り届けてやろうか?ん?」
「やぁ、冬弥くん。それより、冬らしいバルーンアートを考えたんだけど、寄り道して行かないかい?」
同じ学年で隣のクラス、確かストリート音楽をやるチームメイトの東雲彰人と、一つ上の先輩で幼馴染みの天馬司、その彼のショーキャストメンバーで彼女にとっては先輩の神代類。
誰かがいつも一緒にいる。
…忌々しい。
「…おい、類!オレの可愛い冬弥を悪い道に引きずり込むな!」
「おや、司くん。いつから冬弥くんは君のものになったのかな?」
「そーッスよ。大体、冬弥はオレの、相棒だし」
「…彰人。…司先輩も神代先輩も…」
騒ぐ周りに困った顔をする彼女。
綺麗な髪がふわりと、揺れた。
「ありがとう、助かっちゃった」
音楽準備室に連れ込むことに彼女を成功した私はニッコリと笑う。
お人好しっぽいな、とワザとらしく彼女の前で困っていれば彼女の方から声をかけてきたのだ。
…本当に忌々しいったら!
「いや。別に大したことはしていない。…役に立てて良かった」
「本当にありがとう!…ねぇ、青柳さん」
「…?どうし…っ?!」
ふわ、と、首を傾げる彼女の髪を掴んだ。
「い、た…なに…?」
「…いい加減さぁ、ウザいんだよね」
「…え?」
「周りに男侍らせてモテてるつもり?そーいうの、ムカつく」
「…あ、の」
困った顔で私を見上げる彼女にイライラが止まんない。
なんで、そんな顔で私を見るの。
「青柳さんのお父さんって有名な音楽家なんだって?あは、お金持ちじゃん。宮女にでも行ってればこんなことにはならなかったのにね」
「っ、父さんは…っ!」
「そーだ!ピアノ弾いてよ、青柳さん!仮にも音楽家の娘、でしょ?」
「…ぅ、ぁ…」
「やっだぁ、弾けないの?可哀想!なら私が教えてあげる。ほら、来て?」
髪を引っ張って彼女を急き立てる。
…それが、嫌だってことを知っていて。
「ぃ、たぃ…っ!」
「早く来ないからじゃん!それとも何?髪引っ張られるのが好きなんだ??いい趣味ー!なら明日からも毎日、今までのことに加えてやってあげるね!」
「…ぇ?」
呆然とする彼女に私は笑いかける。
絶望を映すその目に私が写りこんだ。
「ね、気づかない??今までの事はぜーんぶ私なんだよ?草薙寧々と探してた貴方の捨てられた教科書も、白石杏が心配してた寝不足の原因である無言電話も、暁山瑞希が怒ってた昼食の行方も!ぜーんぶ私!」
「…っ!どう、して」
「言ったじゃん、ムカつくって。手っ取り早く虐めるなら此処で青柳さんを犯しても良いんだよ?あははっ、彼氏たちは怒るだろうね?」
信じられない、という彼女に私は笑みを作る。
「…今日は一小節弾けたら帰してあげる。弾けなかったら蓋をそのまま閉めちゃうかも?…動けないなら何したって良いよね?」
「…っ!」
「ちなみに明日からも続くからね?逃げたりしたら…分かるよねぇ?青柳さん」
「…わか…」
「逃げたりしたら。…どうするんだい?」
声がした。
振り向いた私に冷水が浴びせられる。
「っ?!!」
「冬弥!…大丈夫か?濡れてないか?」
「…あき、と」
ホッとしたように彼女が息を吐いた。
何するのよ!と激高する私に、東雲彰人は。
「ああ、すみません。…ゴミかと思って」
にこりと笑い、いけしゃあしゃあと言ってのけた。
「ゴミなら処分せねばなるまいな、類!彰人!」
「そうだねぇ、司くん」
ポカンとする私にかけられる二種類の声。
「…人のものに手を出したらどうなるか…教えてやらねば。そうだろう?」
「華は綺麗であるべきだよ。…穢すものはなんであれ排除しないとね」
無表情の天馬司と綺麗な笑みの神代類の対比が恐ろしい。
ちらりと彼女を見れば東雲彰人がこちらを睨みつけていた。
握り締めた拳から血が滴り落ちている。
カタカタと震える彼女は私から目が反らせないようで。
それが何だか堪らなく愉快だった。
だって、彼女が私だけを見ていてくれている!
男たちには目もくれず、私だけを!
「センパイたち、早く片付けてくれねぇとオレがヤバイんスけどね」
「分かっている。オレだってだなぁ…!」
「…ふふ、あはははは!!」
何だか可笑しくなって笑いだした私を、男たちがギョッとした目で見た。
「…行こうぜ、冬弥」
「…彰人」
「僕達はこれを先生に引き渡してから行くよ」
「心配するな、冬弥。もう大丈夫だから」
声がする。
嗚呼、すごく耳障り!
「ねぇ、青柳さん!私、ピアノコンクールで一緒だったんだよ!貴方のピアノ、覚えてる!そんな野蛮な人たちと一緒にいないで私と来てよ!短い髪は似合わない!ねぇ、だから…っ!」
そこまで言った私の意識が揺さぶられる。
数秒遅れて痛みが走り、聞こえてきた声に私は殴られたのを悟った。
そうして、彼女は忌々しい男たちに取られたのだ、ということも。
「…二度と…二度と冬弥に手を出すな!!!」
揺れる、彼女の髪。
歪な旋律は、こうして終曲を…迎えた。
(これは、歪んだ乙女の恋愛狂詩曲)

![SF STUDIOS The Falcon and The Winter Soldier Season 1 - STEELBOOK [-] [-]](https://m.media-amazon.com/images/I/51tLcIMHq-L._SL160_.jpg)




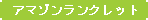
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments