いざ向かうは愚者の楽園
悪事の共有は蜜の味。
ピンポーン。前触れなく響いたインターホンの音に、冬弥はびくりと肩を揺らした。本を閉じてから見た先の時計はもう11時半を指している。すっかり深夜だ。
そんなに時間が経っていたのか。意識に誘われるように出てきた欠伸を噛み殺し、パーカーを羽織り玄関へと向かう。彰人がこれから行く、とメッセージを送ってきたのは10時半頃のことだったから、1時間は経っていることになる。いつもは遅くとも30分くらいで家に着くのに。何かあったのだろうか、それとも。冬弥は少し首を傾げた。胃に溜まってゆくような居心地の悪い違和感がある。
そしてサンダルを突っ掛け鍵を開けようとしてから、はたと思い留まった。だって、彰人ならこの家の合鍵を持っているはずだ。一度も忘れたことはない。それなのに何故わざわざインターホンを押したのだろう。手を引っ込める。
ピンポーン。もう一度、安いチャイムの音が鳴った。今度は明確に、どきり、と心臓が嫌な声を上げた。
普通に考えれば、ドアを隔てたそこには彰人がいるはずだろう。こんな遅い時間、冬弥の家を訪ねる者など彰人しかいない。けれど冬弥は近頃恐ろしい視線を肌で感じることがあった。実際に後をつけられたという証拠も確信もないが、ただ、感じるのだ。視線。見られている、という感覚。
小さなドアスコープが途端に冷たくこちらを睨みつける。それは彰人を写しているはず。向こうにいるのは彰人なのだ、きっと。分かっていても嫌な汗が背を伝う。勘違いだと笑い飛ばされても仕方のないような、ただの視線に刺される感覚にここまで怯えているのかと、はじめて自覚し驚く。
冬弥は足音を立てないように、なるべく慎重に一歩踏み出し、身を屈めた。落ち着くため、息を吐く。肺に残る酸素をすべて出してから、思い切り息を吸う。そうして息を止めて、ドアスコープを覗き込んだ。
「……っ、はぁ」
見慣れた橙の髪、一房のメッシュ。俯いていて顔は見えないけれど、確かに彰人だ。
冬弥は安堵に息を吐き出し、体を起こす。緊張に固まっていた体を緩めて、すぐに鍵を回した。合鍵を使わなかった理由をあとで問い詰めなければ。思いながらドアノブに手を掛けたが、冬弥が開けるより先に勢いよくドアが開けられた。
自ずと体がつんのめる。全身にぶわりと冷気を浴びた肌は震え上がり、瞳は凍りそうに痛んだ。きゅ、と目を瞑った冬弥を彰人は受け止めて、玄関の中に押し入るようにはいってくる。
「冬弥、」
「え、あ、彰人?」
突然の熱い抱擁に戸惑い彼の名前を呼ぶ冬弥の声は、玄関のドアが閉まると同時に外へと逃げて行った。一際大きな重い音がすると世界が隔たれたようで、彰人と冬弥の発する音のみを耳が敏感に拾う。
彰人は酷く息が上がっていた。そしてそれを抑えようと必死になっているように見えた。冬弥は暫く、いつも以上に強く抱き止める彰人の強い力にされるがままでいた。時折服が擦れる音がしては、より一層力が強くなった。
明らかに様子がおかしい。うっすらと漂う香水の甘い香りの隙間から、生温い土の匂いがする。髪はライブ後と変わらないくらいにへたっていて、それは今尚こめかみから伝う汗のせいらしかった。それに、明日は雪の予報だというのにアウターすら着ていない。分厚いパーカー一枚だけで、それでも体は熱かった。縋るように掻き寄せる指先だけが冷たい。
どう考えたっておかしいけれど、冬弥は何も言わなかった。それは優しさなんかではなくて、彰人ならばそうすると思ったからだ。まずはこうして、受け止める。空想の彰人がする行動が優しさ故なのであれば、もしかしたら優しさなのかもしれないが。
冬弥を上から抱え込み、何かから守るようにして心音を穏やかにしてゆく彰人はその何かに怯えているように見える。黙ったまま彼の広い背を撫でて、抱きしめられたままでいるのが現状出せる最適解なのだ。
「大丈夫、か」
どれくらいそうしていただろうか。長かった静寂を終わらせたのは彰人のそんな掠れ声だった。冬弥の体を確かめるように辿りながら腕を緩める。
大丈夫かと、そう尋ねる彰人のほうがよっぽど大丈夫じゃないだろうとは思ったが、冬弥は彰人にだけ聞こえるような声で「大丈夫だ」と答えた。彰人は虚な瞳をこちらへ向けてからふいと逸らした。そうして強張っていた体を脱力し、ゆらゆらと玄関に座り込む。
冬弥の足元でその体躯を丸める彼は酷く小さく見えた。それが不思議で、サンダルをとりあえず脱ぎ彰人が腰掛ける隣で目線を合わせてみても、やはり小さい。
彰人はいつも大きな存在だった。揺るぎない、変わりのない芯はいつだって冬弥の道標だ。大樹のように確かな根を張り、ちょっとやそっとのことでは枯れない。思わず頼ってしまうようなあたたかい強さだ。葉を落とし、風に揺れ迷うことはあれど、礎は変わらず同じ場所にある。いつだって強く、大きかった。冬弥に対しても、その上自分自身へも、そうあるようにしていた。喉に込み上げた弱音を自覚して尚飲み込んでしまうようなところがある。
だからひとりで溶かしてきたその脆弱が見え隠れしているのが、明らかに何かがあったのだと冬弥が確信に至る理由だった。そしてそれを隠してしまわないで欲しい、とも思った。不安を分け合えば半分になる、なんて戯言は信じていないが、冬弥は寄り添ってきてくれた彰人に何度も救われているから。
「彰人」
「…………」
「とりあえず、リビングに入ろう。ここじゃ暖房が効いていな───」
肩を押され、言葉が途切れた。近くで見た瞳はなんだか濁った色をしていて、彰人はそれを隠すみたいに視線を落とす。下を向いた睫毛が震えている。違う、睫毛だけではない。両肩を掴む指先も、短く吐き出される息さえも。寒いから、というわけでないことはなんとなく分かった。
背が壁の冷えた温度に染まっていく。冬弥が一度、二度、とまばたきをすれば、その度に彰人の唇が近づいた。スローモーションのようだと思った。全身が覚えておけと叫ぶから、痛いほど目に焼き付く。ゆっくり、まっすぐに冬弥を求める唇。
いつだって止めることは出来た。体を揺すり、顔を背け、名前を呼んで。方法はいくらでも思い浮かんだ。けれど冬弥はひとつも実行しなかった。そうするべきだと思ったし、そうしたいとも何処か思っていた。
うるさいほどの静けさの中で重なった唇は、縋るように震えていた。冬弥は瞼を閉じ、大丈夫だと伝わるように彰人の後ろ髪に手を回し、引き寄せ、深く重ねた。これは何も間違いではないと言い聞かせるような熱を捧げる。
力を込めて手の震えを抑えるように、彰人は冬弥の唇を強く食んだ。一度離れ、しかしもう一度重なる。冗談だと言い逃れする道を絶ってゆく。逃げ道など端から必要としてはいないが。
そうして何度も、何度も繰り返した。唇のあわいは少し開いていたけれど、見えない壁があるかのようにその先へは侵入して来なかった。ただ柔い唇を合わせる。手入れを欠かさない彰人の唇は、今日に限ってかさついていた。
「……彰人」
唇を離し、ずる、と手を離した。パーカーが一緒になって肩から落ちる。冬弥が汗に濡れた頭を引き寄せると、彰人は大人しく冬弥の胸元に収まった。
冬弥は自身の心音を聞かせながら、彰人が何か言うのをじっと待つ。なにかあったか、と聞いても良かった。しかし、そんなこと聞かずとも彰人は吐露してくれるだろうと思っていた。そうでなければ、彰人はすべてを笑顔の下に仕舞い込んで平気な振りをしているはずだから。
そして彼がもし自分を頼ってくれるのならば、何を言われたとしても受け止めるだけの覚悟はあった。それは今に限ったことではなくて、きっともう随分と昔から。
「冬弥。……オレ、……」
「……ん」
「オレ……さ、」
彰人はごくりと唾を飲み、震える喉で深呼吸をする。溺れてしまいそうな覚束ない息継ぎ。
「人を…………殺したかも、しれなくて」
噛み潰すように小さく、低く、掠れた声で告げられたその言葉は、冬弥の頭をぐらりと揺らした。
一瞬理解が出来なかったのは、現実からかけ離れた突飛な告白だったからだろうか。殺人。さっきまで本の中で探偵が解決しようと勤しんでいたこと。
誰よりもまず冬弥を頼ったのは、共犯への誘いか、それとも最後の審判の真似事か。そんなことは考えていないかもしれない。自ずと指先が震える。反して、彰人は落ち着いてきている。
まさかと驚いて、問い詰め、諭し、正しさをぶつけることは誰にだって出来ると思った。余程のことでなければ法に則った話をしていたのかもしれない。そして、彰人が求めているのはそういう正論なのかもしれないとも思った。しかし、湧き出る冬弥の本心は今、別のところにある。
「……まずは暖かい部屋へ行こう、彰人。外は寒かっただろう」
ただ、冬弥は酷く冷静であった。冷静に、頭に過ぎったさまざまな未来を傍に置いて、本心を優先しよう、と思った。
彰人と共にいたい。それだけだ。
◇
彰人から大まかなことの顛末を聞き、淹れたばかりのホットコーヒーをほとんど残したままふたりは外へ出た。冬の夜は凶暴だ。肌を刺す空気に冬弥は鼻を小さく啜った。彰人に貸したアウターはシンプルかつ黒色の、目立たないダウンジャケット。寒そうに鼻先までチャックを上げていた。似合っているな、と思って、少し微笑む。
そうして、人通りのない暗い道を歩いた。家を出る時にはとっくに日付を跨いでいたから、もう終電も無くなっているだろう。ここらに立ち並ぶのはアパートや一軒家ばかりで、駅からは遠い。冬弥がそんな場所に一人暮らしを始めたのは、単純に間取りが気に入ったこともあるが、公園が近いことも大きかった。いつでもふたりで歌える場所。歩いてすぐだ。しかし、今日に限っては遠く感じる。
「しりとり、しようか」
「は? しりとり?」
「りんご」
勝手にゲームを始めた冬弥を彰人は暫く見つめてから、「ごりら」とパスを返した。「らっぱ」「ぱんだ」「だるま」と続く言葉のラリーは、彰人が余計なことを考えなくて済むように、と思いついた子供騙しの遊び。深刻そうにきゅ、と寄せたままだった眉間の皺が薄れる。
すこし広い公園の、その入り口。砂利を転がす軽い音は昼と違ってなんだか静かだ。鉄棒、ベンチを通り過ぎ、だだっ広い遊び場を歩く。ひとつ、またひとつ、幼い単語でしりとりをして、薄雲のような息を交互に吐いた。その馬鹿らしさに冬弥は笑った。釣られるように彰人も微笑んだ。これから対面するのは死体かもしれないというのに。
互いに口を閉ざして、彰人は足を止めた。
冬弥がまず引っ掛かったのは、「かもしれない」という言い回しだった。断言されていない。それに、彰人が自ら誰かを殺める行為などするはずがない。小説でだって、事情を聞くところから始めるのだ。冬弥も同様に、ホットコーヒーを出した後、「順を追って聞かせてくれ」と頼んだ。
彼が言うには、駅から冬弥の住むアパートまでの近道である公園を抜けようとした時、様子のおかしい女性に声を掛けられたらしい。11時頃のことだ。彼女は最初、道を尋ねるようにしていたが、途端に包丁のような刃物を取り出し襲いかかってきたという。咄嗟に避け、揉み合っていると彼女はバランスを崩し花壇の角に頭をぶつけて倒れてしまった。アウターに返り血を浴びるほどの衝撃で、だらだらと止まらぬ鮮烈な血液を見ていたら恐ろしくなり、木陰に彼女を隠した後急いで冬弥の家まで来た。
彰人はぽつ、ぽつ、と話す間少しもコーヒーを飲まずにいた。「脈は確認したか」と問えば首を横に振り、「合鍵は」と問えばジーパンの両ポケットを探り、ほっとしたような顔で鍵を取り出しテーブルの上に置いた。「あの時は必死で」と付け足すように呟くと、蒼白な顔を隠すみたいに俯いた。
彰人の話に疑いの余地は無かった。嘘など吐かれたことがない。例え嘘であっても、それを暴く術を持ち得ない。彰人を信じることが今出来ることであって、今までもしてきたことだった。
「今からその女性を隠したという場所へ行こう」
「今から……」
「ああ。殺したかどうかは分からないということだろう? 先にその確認が必要だ。今は……12時を回っているから人通りもないと思うが、万が一誰かに見つかったらそれこそ困る」
言いながら、何に困るのだろうかと思っていた。埋めたりでもするつもりなのだろうか。小説で得た半端な知識だが、やり方くらいは知っていた。しかし、同様に法律の知識も少しだけある。こういう場合は余程のことがない限り、重い罪には問われない。正当防衛だと証明が出来れば。
彰人と一緒にいられれば何だって良いと思う。
殺人をしておいて普段通りでいられるほど狂った男ではない。そのために罪を償うと言うのならば、それが良いと思う。けれど、もし隠蔽したいと言うのなら。例えば追っている最中の夢のために。そうしたら、冬弥は埋めることだって隠すことだって出来るかもしれない。逃げたいと言うのなら、けして冬弥を置いていかずに、必ず連れて行って欲しいと思う。
だが、どうすれば良いと問われたなら。罪を償ってきてくれと言うだろうな、と思った。そうして、誰に何を言われても冬弥だけは隣にいる。歌を、歌う。
冬弥の隣に彰人がいて、彰人の隣に冬弥がいる。そうであればもう、冬弥は幸せだった。
とはいえもしものことを考える前に、まずは現状を把握しないといけない。
「アウターは貸す。この間彰人に見繕ってもらった、あの」
「あー、あれは……色が派手だし、ちょっと奮発したやつだろ。どうでもいい服とか、ねえの」
「彰人に見立ててもらったものばかりだからな。どうでもいい服なんてないんだ」
「……それじゃあ、地味なやつ」
これから死体を確認しに行くとは到底思えない会話だった。人間案外平気でいられるものなんだな、という発見は、人を埋める想像をチラつかせた。
いくつも木が並び、その前には花壇がずらりと並ぶ公園の端。そこを前にして彰人はぴたりと動かなくなって、冬弥も一緒に立ち止まった。立ち昇る白が少なくなり、彰人の息が上がっていることを知った。
冬弥は彰人のアウターのポケットに手を入れ、ぎゅ、と手を握った。彰人は一瞬躊躇って、それでも力強く握り返す。大丈夫、大丈夫だ。ふたり一緒ならなんだって大丈夫。
手を繋いだのは初めてだったが、不思議と落ち着いた。あの時初めてキスをされ、彰人が落ち着きを取り戻したように。生と死を目の前に、冬弥は奇妙なほど浮かれている。
悪事の共有はセックスなんかより強い麻薬だ。そして、何より恐ろしい愛だ。冬弥はゆるされている。他の誰でもない、冬弥だけが。彰人の罪へ、じかに触れることが出来る。それはともすると、体を重ねる程度のことより何倍も気持ち良いことなのではないか。
冬弥は彰人の心臓に触れるように指を絡め、じっとその横顔を見つめた。
「……もうちょっと、向こうの方だ」
彰人は右の方を指差し、冬弥を見つめ返す。冬弥は小さく頷いて、彰人と同時に一歩を踏み出した。
「もし本当に死んでたら、オレ──」
「彰人」
自首する。そう言いそうだと直感的に思って、咄嗟に言葉を遮った。彰人は虚にこちらを見る。
何故その言葉を聞きたくないのか分からない。実際、冬弥の中では自首を勧める選択肢が脳内を占めていたのに。彰人が言ったら本当にそうなりそうで、冬弥は吐き気を催すほどそれが嫌だと思った。
──……分からない。どうしてこんなおかしい思考回路に陥るのか。罪の麻薬にやられているのだろうか。
「……冬弥?」
「あ、いや。……暗いからよく見えないなと思って。スマホで明かりを付けた方がいいな」
「ああ……。そう、だな」
冬弥がすいすいとスマホを操作すると、ぱっ、と途端に明るくなる。砂利の一粒一粒がよく見えた。
彰人はふう、と大きく息を吐く。
「彰人。……大丈夫か」
「…………大丈夫。ちゃんと自分の目で見るから」
ぎゅ、と手汗に塗れて冷えた手を握り直し、彰人は顔を上げた。その視線の先へ、光を当てる。
そろり、と恐る恐るぼやけた丸い光が動き、やがて真っ赤な液体を捉えた。一色の絵の具を溢したような鮮やかな赤だった。動物的本能で手が震え、まばたきを忘れる。こんな量の血は見たことがない。
「……ここに、頭ぶつけてた」
「…………」
「隠したのはもっと奥のほう」
死の気配を感じる。鼻をつく鉄っぽい臭いと目を刺す皮膚の下を流れる色。すぐ近くに、死のにおいがあった。はじめての経験だった。
それはクライマックスの近い小説のように、冬弥の鼓動を急かす。見たくない。けれど、見たい。見なければいけない。ゆっくりと歩みを進め、ライトで木のあたりを照らす。真っ赤な色がずるずると続いている。
「まだ向こう。……あの木の下」
「……あの、木の」
指さすその先を照らす前、冬弥は決めた。自首はさせない。死体は隠してしまえばいい。それは実際の現場に来るまでは想像で終わっていたこと。血生臭さに脳みそを揉まれた末にぽつりと浮かんだ妙案。
ひとつ、唾を飲む。ゆらりと照らされるおおきな木の下。
「は、……え? ……いねえ。いなくなって、る」
彰人が急いで駆け寄ったので冬弥もそれに続く。
より明るくはっきりと照らされたそこは、小さな血溜まりはあれど女性の姿など見当たらなかった。
冬弥はようやくまばたきを思い出し、冷えきって痛いほどの目を一度強く瞑った。しぱ、と何度か目を閉じ、開く。涙の膜が明かりを小さく反射し景色を輝かせ彩る。それはあまりにキラキラとしていて、神さまからのプレゼントみたいだった。
「本当にこの場所だったか?」
「この場所……。ここ、のはずだ。血も残ってる、だろ……」
「それは……確かにそうだ。それならこの血の跡を辿ってみた方がいいな」
冬弥は今来た道とは反対の方へ点々と続くまるい血痕を照らした。どうやらその女性は即死では無かったようだ。痛みに抗って逃げようとした、その跡はヘンゼルとグレーテルよりも分かりやすく残っている。
もしかしたらその女性は生きているのかもしれない。そうしたら彰人が自首する必要も、そもそもこんなことに悩む必要だって無くなる。冬弥は抱いた希望の答え合わせをするように、その跡を辿ろうとした。
「っ、待て、冬弥」
ひとり歩き出す冬弥の腕を掴み、彰人の声は閑静な街に響く。
「……どうした」
「ひとりで行くな。絶対」
「あ、ああ。すまない」
切羽詰まったような低い声に謝ると、彰人は気まずそうに額を抑えた。
「……あー……違う、悪い、わざわざ着いてきてもらったのにな。……あとそれ。明かり、オレがやるから」
彰人は冬弥の手をもう一度握り、スマホを取り出す。冬弥を背に隠すように立つと、辺りを警戒し見回した。守られるべきは彰人のはずなのに、何故か冬弥を守るみたいな格好だ。
雑草の上に落ちる真紅の痕跡は、歩を進める毎に間隔が広くなってゆく。じっくりと土を踏みしめる。頭をぶつけた女性の追体験をしているみたいだと冬弥は思う。
「その女性はどんな見た目だったんだ?」
いったいどんな人だったのだろう。
冬弥は想像を膨らませるために、今まで聞かなかったことを尋ねた。どうせ実際に見るのだからいいかと思っていたが、どうやら目にすることはないかもしれないから。
そして、こんなことを想像するのはおかしいことなのかもしれないと過ぎった。狂っている。冷静に、しずかに。それはなんだかいいことのように思えた。彰人だっていま十分に狂っている。肩を並べ立つことのできたような、その同等性に冬弥は満足する。
「え、ああ……暗かったからあんま見えなかったが、髪は黒くて……確かここらへんまであった」
彰人は自身の腰に手を当てる。スマホの光がその動きに合わせて足元でチカチカと動いた。
「服は……白っぽいフレアコート……あの、裾が広がってて、袖にふわふわしたのが付いてるやつ。あれ着てたな」
ぼんやりとイメージする。そういうファッションをする人物は大学でちらほらと見かけたことがあった。だとしても冬弥の知り合いにはいない。
生きているのならどうするだろう。もし冬弥なら。少し遠いが徒歩圏内に大きな病院があるから、そこへ行くだろうか。それとも救急車を呼ぶだろうか。あの血の量だ。頭をぶつけたのなら、何針か縫う必要がある。冬弥としては、あれほど血を流してもまだ動けるという事実が既に驚愕だったが。
そして草を分けるような音から砂利を踏む音に変わり暫くした後、彰人は立ち止まり「ない……」と小さく声を漏らした。もうとっくに砂利道に入っていて、公園の出口はすぐそこだ。冬弥は彰人が動かすライトの先を見た。
「彰人?」
「血痕が途切れてる。……もう辿れねえ」
彰人が右、左、とライトを移動させ、少し歩いて先を見てみても赤い色は見当たらなかった。ならばここで息絶えたのかと考えてみても、当の死体が見当たらないのであればそういうわけではあるまい。
暫く周辺を歩き回り、隅まで探した。人ひとり入るかどうか分からない場所さえも欠かさずチェックをした。必ずふたりで。何時間も繋いだままの手は冷水に浸したくらいつめたいままだった。けれど手を離すことはなかった。
これがロマンスのはじまりなら満場一致で0点だろう。死のにおいはつめたすぎるから。
ふたりはそのまま念のため病院までの道をじっくりと確認しながら歩き、その病院の手前でようやく小さな丸い跡が落ちているのを発見した。
もうほとんど朝だった。コンクリートに落ちた血液は赤黒く見えたが、まだ少し湿っている。紛れもなくあの女性のものだ。直感に基づいた確信。
冬弥は彰人と目を合わせようとしたが、彰人はその血痕をじい、と凝視したまま、がくん、と全身の力が解けてしまったようで。
「……オレ、」
言葉を詰まらせて彰人はぐしゃ、としゃがみ込んだ。手が離れた。彰人のスマホがかたん、と音を立てて落ちる。
「はー……、冬弥……、とうや、とうや……」
彰人は顔を深く沈めたまま、仄明るくなってきた空の向こうへ祈りを捧げるように、自由になった自身の両手を握った。
冬弥は自分が神さまにでもなったような心地になった。「冬弥、冬弥」と震える声。けれど彰人の神さまには絶対になりたくないなと思う。今までと同じように、隣にいたいだけなのだ。
「彰人」と小さく呼びかけ、冬弥も腰を下ろす。ダウンで膨れた体はやっぱり大きい。大きく腕を回しぎゅう、と思い切り抱きしめてやると、彰人はもっと強い力で冬弥を抱き寄せた。
「……よかったな」
「おう」
「殺したりなんかしていない」
「してねえ、んだよな」
「していない。彰人はなにもしていない」
「……なにもってことはねえだろ」
「いや。なにもしていない。大丈夫だ」
冬弥の言葉に安心して息を吐き小さく笑う。それを聞いていたら冬弥もほっとして、くたくたに疲れた体がより重たく感じてきた。
生きている、となれば殺害の罪に問われることはないだろう。しかしふと思いつき「女性から訴えられたりはしないだろうか」と冬弥が尋ねれば、「それは大丈夫なんじゃねえか」と、あやふやだが確かな回答が返って来た。理由を言うつもりは無いらしい。彰人が言いたくないのなら無理に聞く必要もない。今までもそうしてきたように。
朝の光は夜の狂気を追い払い塗り替える。もし遺体を埋めたり隠したりなんかしていたら、例え一緒にいられたとしてもこんなかたちでは無かったはずだ。一時の快楽に目が眩み悪魔にまで成り下がろうとしていたとは。今となってはもしもの未来など分かりっこないが、冷静さなど簡単に消し飛んでしまうものなのかとゾッとする。
「帰ろう、彰人」
「……だな。はー、疲れた。今何時だこれ」
「ええと……5時24分だ」
立ち上がり、空を見上げた。日はまだ登っていない。空がほんのりと白み始めているだけ。冬弥の知らないうちに日の出の時刻はだいぶ早くなっているようだ。冬が終わる。
「明日……じゃねえ、今日か。予定とかねえんだっけ」
「当たり前だ。そもそも昨晩ふたりで飲む予定だっただろう。家で飲む時は大抵2日目に酒が残る」
「あー……だな。じゃあちょっと、寝かせてもらう」
「ふふ。いつもはそんな風に改まって言わないくせに。彰人は俺の家を自分の家のように使う」
「そりゃお前もだろ。おあいこだ」
来た道を戻る。ほんのりと明るいお陰でライトはもう必要がなかった。適当に話をして、絵の具を混ぜるように足で血痕と砂利を混ぜた。あんなに何時間もかけて歩いた道は実際ほんの数十分の道のりだった。
引き摺った跡が一番大変で、鳥の囀りをBGMにどうにか血を目立たないようにする。もうすっかり爽やかな朝だった。最後に木の下に置かれたままだった血と土に汚れた彰人のコートを回収し、公園を出た。
「その服はどうするんだ? 彰人のお気に入りじゃなかったか」
「まあな。だがさすがに……捨てるかな。綺麗にしても多分思い出しちまうし……」
彰人は大きく欠伸をして言葉を締めた。滲む涙に濡れた瞳は朝日を浴びてあまい水飴のように煌めいている。昨晩のあの濁った瞳ではない。冬弥は微笑む。彰人も微笑みを返す。
思い出すのが嫌ということは、トラウマになってしまったということかもしれない。見知らぬ女性が刃物を振り翳してきたのだ。大丈夫かと尋ねようか考えて、けれど晴れやかな表情を見ればわざわざ深掘りする必要はないかと思い直った。
「あ~……ただいま~……」
自分の家でもないのにそう言ってアウターを脱ぐと、彰人は一度伸びをする。冬弥も「ただいま」と言って靴を脱ぐ。
正直汗をかき体も冷え切っているためシャワーを浴びたかったが、何よりも眠気が勝っている。明るい外から薄暗い室内に入りそれは尚更だった。おまけに暖房を消し忘れたせいでリビングから寝室までしっかり暖かい。
冬弥はつめたい水で手を洗っても覚醒しない瞼を擦った。
「彰人は……シャワーを浴びるのか?」
「そうしてえんだけど、すっげえ眠ぃ」
「ふふ。俺もだ。……なら、一緒に寝よう。彰人が悪い夢を見ないように、俺がそばにいるから」
冬弥はもうすっかり繋ぎ慣れた彰人の手を取り、ベッドまで引っ張って行った。布団を出す手間すら惜しい。何よりすぐ近くで体温を分け合い、眠りたかった。今まで同じベッドで寝たことがないなんて瑣末な問題だった。
付き合っているとか、付き合っていないとか、キスをしたとかしていないとか、そんなことさえもはやふたりの前では意味を成さなかった。
「つめたいな」
「こんなんすぐにあったかくなる」
狭いし。彰人は付け足して、冬弥の腰に腕を回した。冬弥もぴたりと胸元に寄り添い、ぬくぬくと心臓の音を聴く。それは赤子のパズルのように単純に、しかし美しく嵌まった。はじめからここにあるべきだったとでも言われるように。
あまりの心地よさにすぐ瞼が重くなる。
「……とうや」
「ん……まだ、ねてないぞ」
辿々しい舌触りの声を返すと、彰人はちいさく笑った。声が、からだに響く。
「ありがとな。……本当に。お前がいてくれて良かった」
「ふふ、どういたしまして」
暫くすると彰人の深い寝息が聞こえてきて、冬弥は一安心する。ちゃんと、少しでもこうして寝られて良かったと思う。
冬弥は眠りの海へ入る前、ぼんやりとこの夜のことを思い返した。もう二度とないような暗澹たる夜。
この数時間の悪夢を冬弥は大切に抱きしめた。いっとう美しい箱に入れ、鍵をかけ、心臓のいちばん奥のほうへ仕舞い込む。何度も色鮮やかに思い出すために。何度も気持ちよくなれるように。
◇
肌に纏わりつくような真っ暗な夜。あの公園だ。冬弥の住む場所の近くにある公園。彰人はいつものようにそこを突っ切ろうとしている。白い息が立ちのぼる。寒いと思っているだけで、実際その感覚は無い。
すぐに夢だと分かった。公園を歩く自分を上から見ているような、しかし普段の一人称視点でも景色が分かるような、夢特有のあれだ。そして自分の思い通りにはいかないのが夢の鉄則。
「あの! ……す、すみません」
「……? はい。なんですか?」
ああそうか、と彰人はぼんやりと納得がいった。悪いことをしたからなのか、トラウマになっているのか、はたまた彼女の怨念なのか知らないが、数時間前の出来事を夢の中でシミュレーションさせるらしい。自身の口は不思議とそっくりそのままあの時の言葉を奏でた。舞台でも見ているみたいだ。悲劇か喜劇かと考えれば、悲劇。しかしそう言い切るにはあまりにも醜い有り様だろう。
「あ、青柳、冬弥くん──冬弥くん、のところ、行くんですか」
「……冬弥のお知り合いですか?」
「行くんですか」
「えー……
金切り声で捲し立てる。寒さに冷えた耳が更に痛んだ。根拠のない気の狂ったような言葉に、彰人の瞳はすう、と細められる。嫌悪感を隠す気はなかった。そして彼女は彰人の表情を見ると、ふう、ふう、と獣のように息を荒げていった。
「……録音した。通報するから、じっとしてろ」
嘘っぱちだったが、第三者に介入してもらう他ない。彰人がスマホを取り出すと、彼女はぶつぶつと何か呟く。小さく逼迫したように繰り返すのは「なんで、なんで」という言葉で、それが聞き取れた時には既にバッグから刃物を取り出していた。包丁。
言葉になりきらない錯乱した声を上げ彰人に向かって振り上げる。
刃物を持っていた、という事実は彰人の心臓を酷く揺さぶった。それは自身に対する危機感ではない。もしかしたら冬弥に危害が加えられたかもしれない、という可能性が生じたからだ。
「……チッ、っぶねえな」
「いや、いや! 触るな、きもちわるい! 通報してやる!」
「静かにしてくれよ、もう」
避けるのは簡単なことだった。小枝ほどに細い手首をぎゅう、と握り揺さぶると、刃物はぽろりと手を離れ地面に落ちる。彰人はそれを踏みつけ遠くへ蹴り飛ばすと、長い髪で隠れたそいつの目を見た。ぐい、と小さい体躯を引っ張り上げるようにして、無理やりにでも目を合わせる。
彼女は息を詰め、それでもキッと睨むように彰人を見つめた。
「冬弥のとこ行ったのか」
「……うるさい、うるさい」
「行ったのか、って聞いてる」
「あんたさえ、あんたさえいなきゃ」
彰人の問いかけには答えない。こんな女に冬弥が傷付けられるなんて、そんなことあってはならない。いち早く決着を付け、冬弥のもとへ行かないといけないと思った。
だから、この女が邪魔だ。この時、彰人の中を満たしたのは明確な殺意に違いなかった。
「分かれよ。冬弥にお前は必要ない」
「……っ」
「もう二度と近づくな」
番犬よろしく威嚇をしたつもりだった。しかしその声色は言外に「殺してやる」とでも伝えるような、人間らしからぬ声。瞳孔を見開き翳った目玉。
女はびくりと体を揺らし、彰人から目を逸らせない。
「わ、かった……ごめ、んなさ、……っ、もう、来ない……っ、来ない、ですからっ!」
ぶるぶると指先を震わせ、掴まれた手をぐいぐいと引っ張る。彰人が手を離そうとしたのと、その女が力強く身を引いたのは同じタイミングだった。
よろ、と体のバランスを崩し、彼女は後ろへまっすぐに倒れてゆく。そこに、たまたま、花壇があった。すべてが偶然のことのように見えた。しかし、果たしてそれは本当に、偶然の産物であったか?
ごん、と重い音が響いた。ぴっ、とコートへ跳ねた血が、彼女の恨みを刻みつけるように跡を残す。
「……おい」
じわじわと広がってゆく真っ赤な液体。反してさああ、と血の気が引いてゆく女の顔。体を揺さぶる。返事はない。
──……殺した?
さまざまな可能性が頭を過ぎる。冬だというのに体中火照って変な汗が額を濡らした。すぐさま通報し救急車を呼ぶべきだなんてこと、分かりきっていた。しかし彰人はそれをしなかった。
この先に待ち受ける何もかもが恐ろしく感じるが、これで良いと、思ってしまったのだ。だって彰人には明らかな殺意があった。
ずるずると彼女を木陰に隠し、包丁をバッグの中へ押し込み、汚れたコートも一緒にして置いた。彰人にとって今何よりも重要で優先すべきなのは、冬弥の安否だ。
公園を走り抜ける。いつになく脚が重い。そういえばこれは、夢だった。出口に辿り着かない。息が上がる。怖い。きもちが、わるい。
「……っ、は、」
目を覚ました。
知らぬ間に冬弥は仰向けに寝ていて、彰人はそれに縋るように抱きついていた。
「……ぅ、……っ」
胃の中を掻き混ぜる不快感に彰人は口を抑え、急いでベッドを抜け出す。ばたばたと必死でトイレに向かい、ドアを開けた。
「ぉえ……っ、ぅ……! っ、はあ、げほ、」
びちゃ、びちゃ、と胃に入っていた僅かなご飯の残り滓と胃液が真っ白な便器を汚した。深呼吸を繰り返す。喉がびりびりと焦げるように痛い。黄ばんだ生臭い液体を見て何度か嗚咽を繰り返す。口の中に蔓延る胃液が唇から糸を引いて垂れ落ちた。胃の中は空っぽだというのに、内臓まで引き摺り出そうとするような吐き気がする。
こんなの、最悪だ。あいつに向けた殺意の刃が、翻って彰人の喉元を貫いている。抜けそうにない、深く深く突き刺さった刃。
「は、……っはは」
乾いた笑い声は水の流れる音に掻き消された。
彰人はうれしくて仕方なかった。だってこれは、この痛みは、冬弥しか知らない。ゆるし、ゆるされ、ふたりきりで交わした大きな秘密、その証。
彰人は口の中を、そして唇を濯ぎながら、あの口づけを思い返す。ひとの熱、愛のかたち。あの瞬間彰人が求めたそのもの。彰人の罪を受け止めた唇はマリアのように柔くあたたかかった。
つきり、喉が痛む。それさえも──いや、それこそが、酷く愛おしい。
「あきと……?」
洗面所を覗いた冬弥は掛け布団を肩から引き摺り、眩しい光に険しく目を細めた。
どうやら起こしてしまったらしい。時計を見てみると、時刻はまだ9時を回ったばかりだった。
「悪い、起こしたか」
「ん……なにか、あったのか」
「いいや。便所行ってただけ。もっかい寝ようぜ」
冬弥を布団ごとぼふりと抱き込み、寝室へと戻る。くすくすと笑い、布団が丸ごと震えた。まだ温もりを残すベッドに横になり、何も言わず身を寄せた時、彰人は恐ろしいほど幸せで。
「一緒に住むか」と提案を呟けば、冬弥は「それはいいな」とすぐに答えた。
「一緒に住んだらー……」
「ベッドが、おおきくなる」
「ふっ、はは、そうだな」
「そうしたらもっと……のびのびと、彰人を抱きしめてやれるな……」
なんだそりゃあ。矛盾したこと言いやがって。
彰人が返事をする前に冬弥はすとんと眠りに落ちてしまったから、彰人も瞼を閉じる。冬弥のあたたかい腕が、慈しむように彰人を抱きしめている。
今度こそ悪い夢は見ないだろうという安心感に、彰人は再び意識を沈めていった。


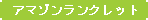
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments