司冬ワンライ/ボカロ曲(アイノウタ/墨汁P)
司は走り出す。
高鳴る鼓動に、息を弾ませて。
「冬弥!」
「…司先輩」
ぶんぶんと手を振れば彼はふわりと目を細めた。
やはり、彼は笑っている方が良い。
その方がずっと似合っている。
「すまない、遅くなってしまった」
「いえ、大丈夫です。…あの、それは…?」
「え?…あ」
冬弥の指摘に司は手元を見た。
小道具で使ったナイフを持ってきてしまったらしい。
よくまあ通報されなかったものだと苦笑した。
「今度のショーの小道具だな。…ちゃんと、偽物だぞ?」
「そこは信じていますが…。…よく、通報されませんでしたね」
「それはオレも同意だな」
顔を見合わせてふは、と笑う。
まあ笑顔で駆けている青年が、ナイフを持っているとは人々も思うまい。
ふと彼がどんな表情をするのか見てみたくて、す、とナイフを突きつけて見せた。
冬弥は一瞬驚いた顔をしたが、柔らかく微笑んで見せる。
「どうかしましたか?先輩」
「…いや…驚かないんだな」
「そうですね。…先輩だから、でしょうか」
予想外の反応にこちらが驚いていれば冬弥がそんな事を言った。
「オレ、だから?」
「はい。…先輩ならば、例え本物のナイフを突きつけられても首を絞められても、何か理由があるんだろうな、と思います」
「それは…オレを過信しすぎじゃないか?」
冬弥の言葉に思わず呆れてしまう。
いくら好きな人とはいえ、殺されかけても理由がある、なんて。
「そんなことはないですよ。…きっと、俺にとっても良い世界に連れて行って下さる気がするので」
「例え良い世界だったとしても、今の生活から切り離すような行為だ、お前の仲間たちが許すとは思えん。それに、オレが良いと思う世界が冬弥にとっても良い訳ではないからなぁ」
「…!」
司のそれに冬弥は目を見開いた。
どうかしたのだろうか?
「先輩は何故、そう…?」
「当たり前だろう?オレにとっての愛の歌が、冬弥にとって呪い歌になるやもしれん。幸あれと願うのは一種の呪いなのだぞ?幸福的価値観を押し付けるんだからな」
「…押し付けられた人にとっても幸せかもしれません」
「それはそう思い込もうとしているだけに過ぎん。まあ、オレのこの考えも押し付けといえばそうだが…」
何故だか泣きそうな冬弥に司は優しく笑いかける。
きっと冬弥は父親のことを思い出しているのだろう。
少し聞いただけだが、自分の【幸せ】を提示するのは決して悪いことではないのだ。
だから、大丈夫だ、というように司は笑う。
「人には人それぞれの意見や考えがある。それをどう取捨選択していくかはお前が決めると良い。正解は、自分しか分からんのだから」
「…はい」
「もし迷ったなら、オレの愛の歌で良ければ歌ってやるぞ!いつだって、どんな時だって、な」
そう言ってやれば、涙を浮かべたまま彼は微笑んだ。
「…ねぇ、あれ修羅場かなぁ…」
聞こえてきた声に司はふと我に返る。
そう言えばナイフを持ったままだった。
「まずい!逃げるぞ、冬弥!」
「え、あ、はい!」
ナイフを慌ててカバンに突っ込み、司は冬弥の手を引き走り出す。
まるで騒がしいパレードのように、景色は目まぐるしく移り変わった。
「ふふ、…」
「あ、笑っているな?!お前、割と大変な時にー!」
「すみません、でも…何だか楽しくて…」
彼の笑う声が空に還る。
きっと、きっと幸せだけではない日々だとしても。
それでも、こんなドタバタで騒がしい歌を、それを幸福とする冬弥を、司は一番に愛してる。
(お前とオレの音を連れて、さてどこに行こう?)
ありふれた毎日を超えて、聞こえる音はアイノウタ!
……
高鳴る鼓動に 息弾ませて
進め足音 行く先知れず
好き・嫌い 君と僕あいこ
ナイフ突きつけ 泣き笑ったら
壊れた音で耳ふさいで
空にこぼせ愛の歌
今日もありがと 明日はさよなら
語れ言の葉 聞く人知れず
今・昔 始まりと最後
首に手をかけ ほほ笑んだら
祝福の音で口ふさいで
空にまいた愛の歌
偽りと本当のパレード
終わりない終末のループに
飽いた 飽いたなら
何処に行こうかな
夢・現 おぼろげな回路
幸あれと 呪いをかけたら
誓いの音で目をふさいで
空にとかせ愛の歌
いつか君と僕のパレード
ありふれた 毎日越えたら
始まりの音で身を包んで
空にとんだ愛の歌
![Old Henry [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41uAZM9N0DL._SL160_.jpg)





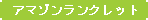
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments