ロマンス未満の掌と
目の端で赤色がちらちらと踊っている。しゃんと背筋を伸ばして歩いている冬弥の足元、スカーレットの靴紐。ほどけそうだ、とぼんやり思っているうちに、それはやがてはらりとほどけ、コンクリートに広がった。
「冬弥、靴紐」
「……? ああ、本当だ。ありがとう」
どうせコンクリートに擦れる音で冬弥自身がすぐ気がついただろう。それでも伝えるべきだと思う。冬弥は自分のことに遠慮しがちだから。
彰人が人の波から抜けガードレールに腰掛けると、大人しく着いてきた冬弥はすっとしゃがみ込む。靴紐がほどけるなんてなんだか縁起が悪いなと思い、彰人は視線を落とした。
真っ赤な靴紐と真っ白な両の手。くるり、紐を丸め、もう片方を巻き付ける。もうひとつ輪っかをつくり、きゅ、と結ぶ。形を整え、今度はしっかりと。ふと、自身の靴紐と見比べる。すらりと伸びた生白い指先から形作られる蝶は、彰人が作るものより随分と美しかった。
「彰人は何にでもすぐ気がつくな」
「……そうか?」
「ああ。俺はいつか……お前無しでは駄目になってしまうかもしれないと、時々考える」
冬弥は立ち上がるとけろりとそう言ってのけて、両手をポケットの中に仕舞い込んだ。立ち上がった拍子にホットミルクのような柔い匂いが彰人の鼻腔をくすぐった。同時に心をくすぐった冬弥の言葉に「そうかよ」となんとなく笑うと、スマホが2度、ポケットの中で震える。
本当に自分無しじゃあダメになってしまえばいいのに。もう何度思ったか知れないそんな残酷な想いを瞳の奥に潜め、メッセージを開く。杏からだった。
「アイツらもう着いたってよ。ちょっと急ぐか」
「そうだな。あまり待たせては申し訳ない」
冬弥の無防備な腰をぽん、と押して人の流れに紛れる。今日はなんだか人が多く感じる。
目的地のライブハウスまではほとんどまっすぐ。ここからであればあと10分程度だ。今回のハコはもう何度も訪れた馴染みのところ。出番も中盤と、なかなか良い時間を押さえられたと思う。早めに着いて軽く声出しでも出来たらいい。杏とこはねは既に二人でやっているだろう。
ちら、と隣を見遣った。今日はどこか落ち込んでいるように見えたが、今はすっかり平気そうだ。朝に聞いた時は「悪い夢を見た」と言っていただけだし、嘘をついているようには見えなかった。とにかく本当にどうしようもない時は言ってくれると分かっている。彰人は密かに安心して、5月の湿った風の匂いを吸い込んだ。
着いた後はどうしようか、と適当に言葉を交わしながら足を進める。辺りは暗くなり始めていた。あそこの角を曲がって、道路を渡って、路地に入って少し。
とうに頭に入ったルートを思い描き角を曲がる。
「……なんだ? あれ」
しかし、そこには見慣れない規制が張られていた。
薄暗い中で目を刺す回転灯と、蛍光の規制線。事故でも起きたのか、普段通っている横断歩道が通れなくなっている。大勢の人はその辺りで滞留し、歩道橋までがざわざわと混み合っていた。思わず「うわ」と声が零れる。
「事故……だろうか」
「みたいだな。向こうから回って行くか」
「それではだいぶ遠回りになってしまわないか?」
「かもしんねえけど……ま、出番には間に合うだろ」
おおよその時間を概算して、くるり、踵を返す。
練習の時間は取れないかもしれない。本番の前にどうにか声を合わせられたら良いが。
「彰人」
少しばかり早足になる彰人を止めたのは、冬弥の声だった。振り返った彰人の腕をぎゅう、と掴み、目の前の歩道橋を指差す。道幅の狭い歩道橋。冬弥がよく見上げては顔を顰めていたところだ。
「あの歩道橋を渡った方がかなり早いだろう」
「……まあ、な」
まさか冬弥からその提案がされるとは。木の上に登って顔を真っ青にしたあのキャンプを思い出す。歩道橋なんて、あれよりもっとずっと高いのだ。
彰人が歯切れの悪い返事をすれば、反して冬弥は微笑んだ。
「俺は平気だ。確かに少し緊張はするが……渡れないわけではない。それに、いざという時には彰人がいる」
こう言われてしまえば、彰人はそれに頷く他無かった。歩道橋の方につま先を向ける。
「……分かった。無理だけはすんなよ」
「ああ」
甘いだとか過保護だとか、そう揶揄われることも増えたが、あながち間違いではないと思う。この世のすべての悪から守ってやりたいなんてヒーローじみた考えにまではいかずとも、ただ、冬弥のことは大切にしたかった。大切に思う人がいることを、分かってほしかった。
例えば色を知らない無地のキャンバスがあったとしたならば。そこに増えてゆく絵の具を、色を混ぜ合わせる姿を、塗りの作法を、すぐ側で見ていてやるべきは自分だと思う。そしてそれが許された唯一だとも思っていた。
恋にも似た想いが混ざってしまったのはいつ頃か、よく思い出せないけれど。
階段を登り終え、振り返る。この狭さでは橋の真ん中を歩かせることはできないだろう。強がっているようには見えなかったから本当に平気だと思ったのだろうが、これでは無理だと言ってもおかしくない。
「冬弥」と名前を呼ぶと、小さな唇をきゅっと結んで頷いた。
「だい、じょうぶだ。……緊張はしてしまうが」
「あんま下の方見るなよ。前歩くから、オレの頭とかこのフードとか……そこらへん見てろ。そしたら歩道橋渡るのなんてすぐだ」
彰人が笑って見せると冬弥は強張った顔を僅かに緩めた。人の波に押されるように一歩、また一歩と進む。
それにしても酷い人混みだ。もともと人の往来が多い場所ではあったが、予想外のルート変更が強いられるとここまでになるとは。牛の歩みで進むのは、冬弥にとっても苦痛だろう。
どうにか気を紛らわせてやろうと、声を掛ける。
「なあ、今度行きたい店があるんだけどさ」
「……行きたい店?」
「おう。古着屋なんだが、パッと見た感じお前に似合いそうな服がけっこうあったんだよな」
「俺に……」
「そんでさ、もうすぐ夏になるだろ。オレも服買いてえし、来週行かねえか?」
「…………」
「とう……っ、うお、」
歩道橋は残り半分を過ぎたところ。いよいよ返事がなくなったなと振り返ろうとした時、体がぐ、と前につんのめった。冬弥が彰人のパーカーを掴んでいる。真っ白な指は更に血の気を失い、その顔は酷く青ざめ、唇は震えていた。
「冬弥」
「……っ、すまない、……」
「謝んなくていい。一旦座れ」
「しかし、……ほかの、人たちが」
「大丈夫。避けて通るくらいは出来るだろ」
すると冬弥はその長身をぎゅっと丸め、空から逃げるように顔を埋めた。行き場を失くした手を握ってやれば、異常に冷えた指先が力無く握り返す。
しかし困った。ここではないが歩道橋を渡ったことは実際にある。ショッピングモールの吹き抜けだって近くにいても問題は無かったのだ。それがあるから冬弥だって平気だと思ったのだろうし、実際彰人も平気だと感じた。今日はいつもと違うのか、それともこの場所が特別良くなかったのか。
とにかく考えるのは後だ。どちらにせよ残りは半分、進むも戻るも同じ。
「落ち着くまでこうしてていいから」
「……ありがとう」
「ん。気にすんな」
自身の体温を分け与えるようにぎゅうと手を握る。こんな状況なのに、冬弥に触れていることが彰人の心臓を叩いて止まない。手のひらだけがおかしいくらい熱くなっているように感じて仕方がなかった。
「…………手、を」
「あ、ああ、悪い、いらなかったよな」
やらかした、と思った。別に彰人の体温なんて求めちゃいないはずだったのだ。ぱっと手を離し、不自然に頬を掻く。彰人は冬弥に何か与えることに慣れすぎていた。無意識に恋を混ぜてしまうほどには。
すると冬弥はいくらか血色を取り戻した顔を上げ、遠慮がちに、彰人の手へ自身の指先を引っ掛ける。
「……いる。安心するんだ」
今度は冬弥から手をぎゅっと握る。彰人ばかりが熱くなっていると思ったが、冬弥の手もあたたかさを取り戻しているようだった。
「手を、握っていてほしい。……渡りきるまで」
「かまわねえけど……もう平気なのか?」
「ああ。あと半分くらいなら平気だと思う」
冬弥は表情を和らげ、小さく頷いた。こんなことを言われて手を握って、彰人の方がよっぽど平気ではないが、どうにか取り繕う。
一緒になって立ち上がり、再び足を前に進めてゆく。実際彰人の方が余裕はなくて、言葉は何も出てこなかった。ただ身体ごと揺れてしまうような心音を悟られぬよう、深く息を吐く。下を通る車の音が遠く聞こえた。人のざわめきが他人事のようだった。
冬弥が再び無理だと思わないかどうか、手の握り方はこんな風だったか、彰人の中にはそれだけしか無かった。
姫でもエスコートするみたいに礼儀正しく手を握って、いよいよ階段を降り切った時、彰人はふう、と一際大きく息を吐いた。冬弥を振り返り、インディゴとペールブルーをぐしゃりと混ぜる。
「しんどかったろ。もう大丈夫だからな」
「……迷惑を、掛けた」
「だから気にすんなって。あそこでちょっと休むか」
名残惜しい気持ち半分に手はするりと解いて、すぐ近くにあったベンチに腰掛ける。顔色はもう青ざめていないが、表情はまだ本調子ではなさそうだった。
ライブハウスまではあと5分ほど。練習は出来るかどうか微妙なところだ。何より、こんな状態ではいいパフォーマンスができないだろう。
「水とかなんか、飲んどけよ。オレちょっと電話かけてくるから」
冬弥が頷いたのを確認して、彰人はその場を立った。杏からの「何かあった?」というメッセージを読んで、彰人はスマホを耳に当てる。ワンコールも経たず、待ってましたとばかりに電話は取られた。
『もしもし彰人? 大丈夫?』
「あー、悪い。冬弥が調子悪くなっちまった。今休ませてるんだが」
『んー、そっか、なるほどね。調子は戻りそう?』
「しばらく休ませたら戻るとは思う」
『オッケー。私たちの出番、後に出来るように交渉してくるね! 冬弥のことよろしく!』
「おう。サンキュ」
1分にも満たないうちに話はまとまり、彰人はスマホを仕舞った。杏のことだ、きっと上手いこと出番を遅くしてくれるだろう。
冬弥に目を向ければ、ペットボトル片手に表情を暗くしている。それさえも美しいと思ってしまうのだから、この頭はどうしようもないみたいだ。隣に腰掛け、名前を呼ぶ。
「杏が出番遅くしてくれるってさ。落ち着くまでこうしてようぜ」
「……すまない、俺は……」
「いいんだよ、こういうのってお互いさまだろ。オレがキツくなった時は冬弥に頼るから、な」
大切にしたいのだ。大切にしていると、伝えたい。直接言葉にするのは野暮だけど。
冬弥はふっと目を細めると、もう何度目か、「ありがとう」と言ってペットボトルの水を口に含んだ。結露が手を濡らす。雫が腕を伝ってゆくのを彰人はなんとなく目で追った。あの手のひらの柔らかさがまだ感覚に残っている。
大切にしたいのならこんな想いを抱くべきでないことは、彰人がいっとう分かっていた。しかし、それでも望んでしまうのだ。恋とはそういうものだった。
「今朝、悪い夢を見たと言っただろう」
「あー、そうだったな」
「ビルのような……何か高い建物から落ちてしまう夢だったんだ。……それを、思い出してしまった。今もまだ少し、恐ろしい」
冬弥は眉根をきゅっと寄せ、困ったように微笑んだ。どうにかしてやりたくて、けれど上手い言葉も何も浮かばずにいれば、冬弥は「だから」と言葉を続けた。長い睫毛が瞳に影を作り、月色の虹彩が隠れる。
「だから……もう少し、手を繋いでいてもいいだろうか?」
「……え、」
「そうしていると、なんだかとても安心する。安心したんだ。……駄目だろうか」
ああ、本当にこいつは。
申し訳なさそうに彰人を見つめるその表情に、彰人は観念して手を差し出す。こんなの惚れた方が負けなのだ。
冬弥こそ早く、彰人に惚れてしまえばいい。投げやりな考えを手のひらに込め、重ねた手をぎゅ、と握った。


![Blade Runner 2049 (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lkpGNMBgL._SL160_.jpg)

![MJLN Bettany Hughes' Treasures of the World Series 3 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41y2recaQQL._SL160_.jpg)
![Power of Grayskull: The Definitive Histoy of He-Man and The Masters of The Universe [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/5145MCpRc3L._SL160_.jpg)
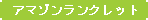
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments