中秋の黒猫(ザクカイ)
「お月見をしよう」
さて誰が言い出したのか分からないそれは、珍しく全員を巻き込んだ行事となった。
花見もやったのだから、と言われてしまえばまあそうかとも思わなくもなかったが。
「…十五夜はもう少し先ではなかったか…??」
先程伝えそびれたそれを呟いたザクロは小さく溜息を吐く。
確か、十五夜は年に寄って日付が変わるらしいのだ。
今年は10月1日だったような、と思いながらもまあ皆が楽しそうなら良いか、とも思う。
しかし彼はどこに行ったのだろうかと上を見た。
先程からカイコクを探しているのだがまったく見当たらない。
全員で月見を、と言われているのに一体どこへ、と息を吐いた…その時。
「ひっ、うわぁあっ?!」
「…は?!!」
短い悲鳴と共にカイコクが月から降ってくる。
目を見開き、無意識に手を広げた。
「…つー…。…あ、忍霧」
「…重いんだが…?!」
「…お前さんが勝手に俺の下にいんだろうが…っと」
自分より背も高く体重もそれなりにある彼を支えようなんて方が無理で、重く鈍い痛みに文句を言ってやればカイコクはあっさりそう言う。
よっと、なんて軽くしなやかに立ち上がる彼をブスくれた目で見つめた。
「んで?お前さんは何しに来たんでぇ」
「月見をやると言うから、逃げた貴様を探しに来てやったんだが?」
「…わざわざご苦労なこって」
嫌そうにカイコクが言う。
ザクロを認め、木の上にでもいた彼は逃げようとして足を滑らせたのだろう。
運動神経は良いくせに、と呆れながら…ふと思う。
追いかけられるのは嫌いではある彼だが…はて月見もあまり好きではないのだろうか。
そう思ったのはカイコクはなんだかんだ律儀だからである。
花見もキャンプもイベントも、何のかんの言いそうな割には毎回きちんと出ているのだ。
ザクロが嫌だからと言って逃げたりはしなかったのに。
「…鬼ヶ崎。月見は嫌いか?」
「嫌いつーかまあ…」
言葉を濁す彼をじぃっと見つめれば最初は嫌そうにしていたカイコクがホールドアップの姿勢を取った。
「わーった。…月見にゃ団子だろう」
「…?まあ、定説はそうだな」
「大体は味がねぇ。だから餡子をつける。俺はそれが嫌なんでぇ」
本当に嫌そうな表情の彼に、そんなことで、と言いかけてやめる。
カイコクは甘いものが苦手なのだ。
ザクロとて辛いものは苦手だから、味覚如き、と言えないのである。
代わりに持ってきた魔法瓶を差し出した。
「…?何でぇ」
「開けてみろ」
首を傾げる彼にそう言えば素直に受け取り蓋を開ける。
「…!こりゃあ」
「…。伊奈葉に感謝するんだな。貴様が甘いものは苦手だと知ってわざわざ作ってくれたのだから」
目を見開くカイコクに言ってやり、瓶を取り返してコップ部分にそれを注いだ。
中に入っていたのは白玉入りの豚汁で。
これなら皆さん食べられますよね、と笑っていた彼女は想像に難くなかったのだろう、カイコクも小さく笑う。
「…ここまでされちゃあな」
コップを受け取り、それを口に含んだ。
途端にびくりと肩を震わせる。
「っ」
「どうした?」
「…いや、熱かっただけでぇ。味は美味い」
「そうか」
「伊奈葉ちゃんに礼を言いに行かねぇと…忍霧?」
ふわり、と首を傾げるカイコクをぐい、と引っ張り、マスクを外して口付けた。
「…っ!ふ、ぁ、ん…」
甘いものが嫌いなくせに、いとも簡単に甘くとろける彼が、可愛いな、と思う。
「…は…。…何すんでぇ!」
口を離した途端、キッと睨むカイコクにザクロはマスクを押し上げた。
「火傷をしたようだからな、舐めてやろうかと」
「…お前さん、何処でそんな…」
「さあ、何処だろうな」
呆れた顔のカイコクに含み笑いをしながら言えば彼はムッとした顔をし。
「おわっ!だから重いと…!」
「まだ口の中が熱いんだが?…責任取ってくれるよなぁ?忍霧??」
ザクロを押し倒し、蠱惑的に笑うカイコクに最初は睨んでいたが諦め、再びマスクを下げた。
こうなれば意地でも退かないだろう。
この可愛らしい黒猫は。
月にはうさぎが定説だが、カイコクはどう見ても猫だ。
自由で優雅で、それでいて甘えべたの。
夜に映える黒猫は、秋の綺麗な月に照らされ…やがて暗闇に解けた。
(その後はどうなったかって?
それは月だけが知っている)






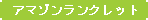
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments