類に懐き出す冬弥を精神的に追い詰める司、の司冬
「…お?」
クラスから出て、さてショーの練習に向かうかと思っていた司の目に飛び込んできたのは思いもかけない組み合わせであった。
「類…と、冬弥?」
類のクラスの前にいたのは類と冬弥である。
自分の教室前なのだから類がいるのは分かる…が、冬弥はどうしたのだろう。
声をかけようとし…司はそれを止めた。
あの冬弥が存外楽しそうな顔をしていたから。
冬弥は感情があまり外に出ない。
本人もそれは気付いているようで、「如何すれば良いでしょうか」と聞いてきた時もあった程だ。
だが、今は如何だろう。
「…あんな顔も出来るのか」
思わず小さく呟いてしまうほど、冬弥の表情は軟らかかった。
いい事じゃあないか、と思うのに如何にももやもやした思いが止まらない。
冬弥が笑いかけるのは、あんな優しい顔を見せるのは自分だけだと思っていたから。
何かあれば司を頼っていた少年は色んな人に色んな顔を見せるようになっていた。
それを、シンプルに嫌だ、と思う。
よりによってそれが類だなんて。
同じ先輩という存在、加えて類は最近冬弥と知り合ったはずなのだ。
彼が幼い頃から一緒にいた自分とは訳が違う。
…それなのに。
「…司、先輩?」
冬弥の柔らかい声が聞こえる。
振り向いた先にいたのは…どうやら類とは別れたようで、冬弥一人だけであった。
好都合だ、と思う。
笑みを作り、冬弥じゃあないか!と態とらしく声をかけた。
「どうしたんだ、冬弥!まさかオレに会いに来たのか?!」
「…いえ。今日は神代先輩に会いに来ました」
はい、と言ってほしかった思いは打ち砕かれ、一番望んでいないそれを引き出す。
「…類、に」
「はい。頼まれていた本が入ったので届けに」
「ほう…。…随分、その…類と仲良くなったのだな」
笑いながら聞けば彼は僅かに微笑んでみせた。
…嗚呼、自分は彼が望んだように笑えているだろうか。
「神代先輩が、芝居関係の本を探していたみたいで…。学校の図書室にはなかったから、図書館に案内したんです」
「図書館に案内?冬弥が、か?」
「はい。その休日は何もなかったので。神代先輩は最近越してきたと聞きましたので…」
はにかむ彼に、そんな顔をするなと言いかけて唇を噛む。
そんな事を言って、何になるだろう?
「…?先輩?」
「…ああ。冬弥は、優しいな」
首を傾げる彼に冬弥は困ったように眉を下げた。
そんな事は、と言うのは謙遜かそれとも。
「…だがな、類には気をつけろ」
「…え?」
口をついて出たのはそんな言葉で、目を見開く冬弥にこちらも驚いてしまった。
何故、自分はそんなことを、なんて思う隙もない。
「類は、必ずお前を傷つける。ショー仲間であるオレですら何度も危ない目に合わされた。死にかけた事だってある。類の噂を聞いただろう?あいつは人に興味がないんだ」
「…そ、んな」
「…なぁ、オレにしないか?」
動揺した表情の冬弥の手を握った。
綺麗な瞳が真ん丸くなり、司を見つめる。
「…先輩?」
「オレなら冬弥を傷つけたりしない。…昔みたいに、オレが護ってやる」
切々と想いを伝えながら司は握った手に力を込めた。
「…」
「…オレのものになれ、冬弥」
「…つか、さ…先輩…?」
「ファンクラブ名誉会長から、恋人にしてやると言っているんだ。悪い話ではないと思うが」
少し怯えた表情の冬弥に司は優しく笑う。
「それとも、何か?父親のように酷くするかもしれない類の元に行くと?」
「…父さん、と…同じ?」
「そうとも!!縛り付け、心も体も壊すかもしれない。そんな男を、良いと思うか?」
「…ぁ…」
ひゅ、と冬弥の喉から音が鳴った。
それは、確かに司が勝利した…音。
パァッと辺りが光に包まれる。
現れたのは、暗い中に佇むサーカス小屋だった。
手を引き、抱きしめる。
そのまま優しく口付けた。
「…ぅ、あ、せ、んぱ…つか、させんぱ、ぃ…!」
「…大丈夫だ。ここに居れば怖いことは何も無い」
縋る冬弥に司は嗤う。
錆びた舞台に観客はもう、冬弥独りだけ。
望んだセカイを逃さぬよう…ヒーローは偽りの優しさで塗り込められた愛を…囁いた。
![極選!!完熟おばさんのドスケベおしゃぶり100連発 / おかず。 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/613rTm+DSXL._SL160_.jpg)
![カーズ クロスロード [レンタル落ち]](https://m.media-amazon.com/images/I/515VkjqSE-L._SL160_.jpg)




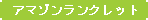
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments