青藍(類冬)
少しショーの練習が長引いてしまった。
吐く息白い、もう夜に近くなった街並みを類は歩く。
日が落ちるのが早くなったなぁと思いながら空を見上げた。
藍に飲み込まれる青色はまごう事無き冬の色だ。
寒いのは得意かと言われればそんなこともないけれど、嫌いではなかった。
寧ろ…と。
「ー♪ー♪」
聴こえてきた歌声に類の足が止まる。
ふらりとそちらへ、方向転換し歩を進めた。
程なくして見つけた人物に目を見開く。
「…君は」
「…。…神代、先輩?」
誰も居ない公園、美しい歌声を響かせていたのは一つ下の後輩、青柳冬弥だった。
響き渡るそれは冬の空に吸い込まれていく。
不思議そうに首を傾げる冬弥から歌声が消えたのを勿体無いな、と思った。
…それを止めたのは類自身なのだけれど。
「…やあ。こんな遅い時間まで練習かい?」
にこ、と笑みを浮かべ聞いてみる。
確か彼はストリートミュージックで仲間たちと何やら目標を立てているらしく、良くその話をしているのを見かけたことがあったのだ。
「…練習は少し前に終わったんですけど。…神代先輩はショーの練習ですか?」
「うん。もうすぐクリスマス公演の初日だからねぇ。皆張り切ってて。…まあ僕も例外ではないのだけれどね」
くす、と笑うと、そうですか、と冬弥も小さく微笑んだ。
それがほんの少しだけ寂しそうに見えて類は冬弥の前にしゃがみこむ。
「…仲間と喧嘩でもしたかい?」
「いえ、彰人たちとの関係は良好です。…ただ…」
「…ただ?」
「…。…少し、帰りたくないなぁ、と」
ほう、と息を吐く、冬弥のそれが白く空気に溶けた。
「…なら、僕もお付き合いしようかな」
立ち上がって微笑み、彼の手を引く。
驚いた表情を見せた冬弥が蹈鞴を踏み、類の傍に引き寄せられる。
「…えと、先輩?」
「フフ、素敵な歌を聴かせてくれたお礼に。君の、缶コーヒー1杯分の時間を僕にくれないかい?」
笑いかけると目を見開き、それから小さく微笑んだ冬弥が、はい、と頷いた。
「それは良かった」
類も笑って見せ、待っていて、と告げてから自販機に向かう。
確か彼はブラック派だったと…座長であり冬弥が尊敬している司が言っていたようないなかったような。
少し迷ってから甘いそれも購入し、冬弥の元へ戻った。
「お待たせ。甘いのとブラックとどっちが良いかな」
「…では、ブラックを」
彼の返答にやっぱり、と思いながら類はそれを手渡す。
「ありがとう御座います。…あの、お金は…」
「可愛い後輩がそんなもの気にする必要はない!…彼ならそう言いそうじゃないかい?君にお金を払わせた、なんて聞いたら僕が怒られそうだ」
「…そう、ですね。…ありがとう御座います」
「どういたしまして。ちなみに、君の相棒くんにも黙っておいてくれよ?遅くまで寒空の下付き合わせたとなれば黙ってはいないだろうからねぇ」
「…分かりました」
類の茶目っ気たっぷりなそれに、くす、と冬弥が笑った。
意外と悪いところもあるのだなぁと微笑み、缶コーヒーを開け、口を付ける。
温かいそれが全身に染み渡り、ほう、と息を吐いた。
「…先輩、クリスマス公演のショーはどんな話なんですか?」
「んー?お楽しみ、かな。まあ一つヒントを与えるとするなら…」
首を傾げた冬弥に笑って見せ、少し考えてから空を指差す。
既に青はなくなり、星が瞬いていた。
「君は、星言葉、というのを知っているかな。誕生日にも割り振られたそれは一つ一つ意味があるものなんだよ」
「…花言葉、みたいなものでしょうか」
「うん、そうだね。ちなみにあの星…」
長い類の指が一つ、星を指差す。
「…ミラク」
「え?」
「知っているかな?アンドロメダ座β星とも呼ばれる星の…その言葉を」
類の問いかけに冬弥は…。
「…いえ、知りません」
静かに、そして困ったようにそう答えた。
なるほど、流石の冬弥も知らなかったらしい。
「フフ、君なら知っているかと思ったのだけれどねぇ?」
「…すみません」
楽しそうに笑う類に、冬弥は困り顔だ。
…別段、そんな顔をさせたいわけではなかったのだけれど。
「今度のショーのテーマなのだけれどね。まあ、答えは自分で調べてもらおうかな」
「…わかりました」
類の言葉にようやっと冬弥も微笑む。
可愛らしい子だな、と思った。
あの司が可愛がるのも、彰人が休み時間の度に教室に出向いているのも納得がいく。
「先輩がお忙しくなければ今度答え合わせをしてもらえませんか?」
「いいとも。お安い御用さ」
冬弥のお願い、に類は微笑んで答えた。
可愛い後輩のお願いだ、叶えてやらない理由はない。
「…ありがとう御座います」
ふわりと微笑む冬弥に、響き渡る前にこの想いを仕舞い込んだ。
きっと彼には必要のないものだから。
強い想いは毒だ。
それはセカイでよく分かっているじゃあないか。
「…神代先輩?」
首を傾げた冬弥に何でもないよ、と笑う。
投げた空き缶は宙を舞い、ゴミ箱へと吸い込まれた。
「それじゃあまた明日」
「はい。また明日」
冬弥が言葉を紡ぐ。
今はそれで良いと…そう思った。
また放課後、あの図書室で
「…知っています」
小さく、冬弥が答える。
金の目を丸くしていれば彼は小さく微笑んだ。
「…本で読んだことがあるんです」
「…そう。なら、僕がそれを君に贈る、と言ったならどうするんだい?…青柳冬弥くん」
冬弥の綺麗な手を持ち上げて口付ける。
ぱちくりと空の色と同じ目を瞬かせた彼は静かに口を開いた。
「…先輩は、その想いを俺に向けてくれるんですか?」
「うん?」
「…俺は、自分の感情がよく分からなくなる時があるんです。だから、先輩が強い感情を向けてくれたら…何か分かる気がして」
冬弥が寂しそうに笑う。
その微笑みは恐らく司も彰人も見たことがないものだろう…ゾクゾクとした。
嗚呼、自分が彼にこんな表情をさせているなんて!
類はきれいで星月夜の如く儚い彼に、瞬くような恋をした。
それは自分が思うより強いそれで。
寒空に響き渡る、この想いに名をつけるならば…。
「君が思う程、綺麗ではないよ?それでも良いかい?」
「…はい」
綺麗に微笑む冬弥の手を引く。
今度は素直に抱かれた彼の頭をなでた。
愛なんて美しいものじゃない。
それでも彼らは夢を魅た。
この想いがなんと呼ばれるかも知らず。
「…神代先輩。俺を連れて…『素敵なセカイにゆきますか』」
「…仰せのままに」
…この日、プロプスはラムダ・ペルセイを連れて姿を消した。
執着心と情熱的な恋


![Testosterone Factor [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41A4F7dVzRL._SL160_.jpg)

![En Vivo [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZwYQODPlL._SL160_.jpg)

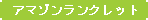
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments