雨とさよならの向こう側で
「…なんでなんだよ……」
はぁあ、と息を吐き出す。
ソファに体を沈みこませて彰人は目を腕で隠した。
頭がぼんやりするのは低気圧のせいかそれとも。
現実逃避をしようとしても彼のあの顔が頭から離れない。
ソファから立ち上がれなかった。
いつだって彼が手を掴んでくれたのに。
…冬弥と、喧嘩をした。
今までそんなこと一度だってなかったのに。
雨も降っていなかったのに彼の頬は雫で濡れていた、気がした。
きっと、そうだったら楽だと…思ってしまったのだろう。
何か訳があったから。
だから冬弥は彰人にさよならを告げた。
耳にこびりついて離れない別れの言葉を無理に押し込んで、とっくに治ったはずの痺れた手のひらをぼんやり見つめる。
冬弥を、殴ってしまった。
だって、彼があんな。
「…くそっ」
思い出せば思い出すほどに疑問しか湧かず、彰人は寝返りを打った。
雨が降った時のグラウンドを思い出す。
酷い泥濘で前に進めない、そんなもどかしさを。
失って初めて気づいた感情に、彰人はまた息を吐く。
こんな感情、歌詞にしか出てこないと思っていたのに。
だが日々は進む。
伝説を超えると誓ったのは誰だった?
パタパタと窓の外で音がした。
ついに降り出したらしい。
それはそれで良いと思った。
雨のせいにすれば、目元が濡れていたって気にならないだろう。
じわりと、暗闇に堕ちていく。
いっそ雨を爆破してしまえばこの感情も消えてくれるだろうか、なんて彰人は自嘲した。
「…雨なんて、いらねぇな」
ぽつりと呟く。
その言葉は降り出した雨の音にかき消された。
「…彰人?」
「……おー…」
彼の柔らかい声に彰人は意識を浮上させる。
どうやら眠ってしまっていたらしかった。
「…わり。寝てた」
「どうした?寝不足か?」
「んや。…早かったな、委員会」
心配そうな彼にひらひらと手を振り、彰人は身を起こしながらそう言う。
今日は業務報告だけだった、と言葉を紡いでいた彼がきょとんとしてこちらに手を伸ばしてきた。
「あ?どうした?」
「いや。…彰人が悲しそうに見えたから、どうしたのかと」
頬にひたりと触れてくる冬弥に、驚きながらも彰人は笑う。
「流石、冬弥には隠し事出来ねぇな」
「…!何かあったのか?」
とても心配そうな冬弥に、彰人は心配するな、と言った。
「…お前と喧嘩した時の夢をみたんだよ」
彰人のそれに冬弥は目を見開く。
そうか、と言葉を詰まらせる彼に彰人は「心配すんなっつっただろ」と言ってやった。
「体育祭の練習とかで離れてる時間が多かったろ。…だから思い出したんだよ、きっとな」
「…トラウマか?」
「はぁ?…当たり前だろ。あの時は本気で冬弥が居なくなるかと思ったのに」
「…それは…すまない」
しゅんとする冬弥を引き寄せる。
ちゃんといるだろ、というように。
「謝るなよ。…冬弥だって同じ想いしたくせに」
「…それは…」
彰人の言葉に冬弥は珍しく歯切れの悪い言葉を返す。
「?なんだよ、言えよ」
それに違和感を覚えつつ促せば、困ったように彼は口を開いた。
「…この寂しさは、彰人を傷つけてしまった罰だと…思っていた」
「……はぁあ?!!」
紡ぎだされるそれに彰人は素っ頓狂な声を出す。
何を、そんな。
「…おまっ、ホント…」
「…すまない」
「…ったく、んな顔すんなよ」
落ち込む彼に何だか逆に清々しくなって彰人は笑った。
自分からさよならを告げてきた彼は、彰人を思ってずっとずっと苦しんでいたのだろう。
全く、やはり雨を爆破するべきだった。
冬弥にそんな顔をさせてしまうなんて。
「…あの喧嘩があったからこそ、オレたちは強くなったんだろ」
「…彰人」
「過去をなかった事にしようとはしねぇよ。…その代わり、二度と勝手には離れさせねぇけどな」
立ち上がり、彰人は冬弥に手を伸ばす。
ああ、と頷いた冬弥がその手を取った。
笑い、その奥の太陽の光に目を眇める。
雨が降らない、この世界で。
泥濘がない路を、冬弥と二人歩いていく。
取り戻した光を、バッドエンドにはさせやしない、と彰人は口角を上げた。
(悲しみをもう一度抱きしめたいなんて滑稽な叫びはしないから
お前からのさよならは、追憶の奥深くに!)


![Testosterone Factor [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41A4F7dVzRL._SL160_.jpg)


![En Vivo [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZwYQODPlL._SL160_.jpg)
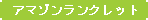
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments