二人のセカイで の詩を
「…なんだこれ」
ぽかん、と彰人はイヤホンを外しながら呟いた。
その反応を見た冬弥も肩を揺らす。
勿論その反応は想定内であったようだが。
「…これ、次のイベントで歌うとか言い出さねぇよな?」
「…まさか。流石に小豆沢や白石に怒られてしまう」
「オレだけなら歌うつもりだったのかよ、怖ぇ奴」
くす、と笑う冬弥に、彰人は流石に呆れた。
彰人が歌うつもりであれば冬弥もノッたのだろうか。
「聴き取れるということは歌う事も出来そうだが」
「恐ろしいこと言うなよ。…口が回んねぇっつぅの」
ふむ、と考え込む冬弥に彰人は軽く笑った。
パフォーマンスで歌う事が出来れば格好も良いだろうが、それで歌詞を聞き取る事が出来なければなんの意味もない。
…存外、正確な音を紡ぎだす冬弥には出来るのかもしれないけれど。
「…もしかして、歌えたりすんのか…?」
「…。…流石の俺も無理だな。早口は向いていない」
「…だよな」
恐る恐る聞いてみれば、少し考えて出されたそれに彰人はホッとする。
「まあ、ドールも私だけで良いと言っているしな」
「…あ?」
くす、と微笑んで言われるそれに彰人は首を傾げた。
何を突然。
そう思っていれば少し楽しそうな冬弥が画面の中の少女を指差した。
バーチャルシンガーである初音ミクとも、自分たちのセカイの初音ミクとも違う姿の少女が悪い顔で歌っている。
「…こいつがドール?」
「ああ。…作者がそういう名前だと言っていたからそうなのだろう」
「ふぅん。なんか単純だな」
彰人のそれに冬弥が楽しそうに笑った。
「名前はどちらでも良いんじゃないか?彼女の意味は『君の詩』を歌うことなのだから」
「…あー、誰にも愛されなかった君の詩、か」
何度か聞いている内に聴き取れたそれを言うと冬弥がコクリと頷く。
「きっと最初は言い付け通りに品行方正に、唄を紡いでいたんだろう」
「まあ、機械だしな」
「だが、君、は周りから愛されないと知る。君、と共に歩んできた彼女は君のためにこの詩を歌い続けているのではないだろうか」
「…あー…分かるような分かんねぇような」
冬弥の言葉に彰人は素直にギブアップを示した。
ミステリー小説好きの冬弥は兎も角、流石にそんなところまで読解出来るほど理解が及んでいるわけではないし、まして考察なんて出来っこない。
事実は、良い歌だが今の自分たちが歌うのは不可能だ、ということだ。
…認めるのは悔しいが。
「いつかドールだけじゃねぇ、オレたちも歌えることを証明しねぇとな。いい曲なのは事実だしよ」
「…!…ああ、そうだな」
冬弥が嬉しそうに微笑む。
その笑顔を見ると、やはり口の体操は毎日しておくか、という気分になった。
音楽プレイヤーを止めようとして…ふと止める。
「…?彰人?」
「いや、やっぱこの曲は歌えねぇなって思ってよ」
首を傾げた冬弥に頭を掻きながら言えばしばらく不思議そうにしていたが、該当の歌詞を見、理解したのか小さく笑った。
「…もしかして」
「…っ、そうだよ。…オレはぜってぇ言わないし、冬弥に歌わせる気もねぇし」
答えを言いそうになる冬弥を遮って彰人は答える。
過激なだけでは別に構わないのだ。
だが、これは。
「俺は構わないんだが。…後生抱いてくれ、ダーリン?」
綺麗に微笑む彼に、何となく煽られている気がしてぐいっと手を引く。
「望み通りにしてやろうか?ハニー」
「…歌の練習が出来ないのは、困るな」
楽しそうな冬弥に黙れと言わんばかりに口付けた。
君には私だけでいいの、と笑うドールが脳裏にチラつく。
それは確かにそうかもな、なんて思いながら彰人は冬弥を抱きしめた。
彰人を求めるような歌は、誰にも聞かせたくない。
(さあさ、共に踊りましょう?
さあさ、共に唄いましょう?)
冬弥の相棒は、彼の様々な歌声を聴くことが出来るのは、彰人だけなのだから!
(それは、冬弥も同じこと)
狭いセカイに、響く二人の唄は、誰にも聞こえず互いの鼓膜を震わせ消えていった。
「…ちなみにこの曲だが、リズムゲーム用に作られたものらしい」
「…あー、それで指を粉砕…」
![【公式】 Shop Japan(ショップジャパン) リバイバルダンス [メーカー保証1年] 健康長寿プログラム ウォーキング以上の運動効果 認知機能改善 有酸素運動 RVD-AM01 ホワイト](https://m.media-amazon.com/images/I/51HUYnrrkvL._SL160_.jpg)



![行け!稲中卓球部 7巻セット [レンタル落ち] [マーケットプレイスセット]](https://m.media-amazon.com/images/I/61q2PFp-a3L._SL160_.jpg)

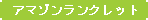
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments