エイプリルフール彰冬
これまで上手くやっていた、つもりだった。
変人と名高い(歌の技術もずば抜けて高いが如何せん行動がそれを上回るのだ)先輩たちとのセッションも勉強になった、これは今後の糧になるだろう。
二人できっと、RADWEEKENDを超えるのだと、信じていた。
そう、今日この日までは。
「…今、何つったよ」
「…。…終わりにしよう、彰人」
冬弥の声が淡々と、練習終わりの部屋に響く。
こんなにも反響しているのに、一向に耳に入って来なかった。
…いつもはあんなにも聴こえてくる相棒の声が。
「…はっ、冗談だろ?」
「…俺が、冗談を言えないのは彰人が一番良く知っていると思ったが」
無表情の冬弥は、確かにこんな冗談は言わない質だった。
純粋で、真っ直ぐで、…音楽にも真摯で。
だからこそ二人で夢に向かって突き進んできたのに。
「先輩方に教えてもらっても夢の一端すら見えてこない。もう、潮時なんだ。…俺は、降りる」
「…テメェ!!!」
感情のない声に彰人はカッとなり冬弥の頬を殴る。
荒い息遣いはどちらのものだったろう?
もう、分からない。
この状況も、冬弥の言葉も、何もかも。
「…。…彰人は、ここに居れば良い。…夢が、消えないように」
「…うるせぇ。二度とその面見せんじゃねぇぞ」
低く言葉を吐き出して彰人は部屋を出る。
乱暴に扉を閉め、しばらく歩いた後ズルズルとその場に崩れ落ちた。
「…なんなんだよ、クソッ……」
彰人の言葉だけが虚しく響く。
…これからだったのに。
曇天から雨が降る。
彰人の周りだけに。
街の喧騒だけが遠く、喧しく響いていた。
それから数日。
ライブハウスでは彰人しか見ないと実しやかに囁かれるようになった。
まあ事実だしな、と思いながら彰人はカバンを持ち上げる。
「…あの噂は…なのか」
「…って」
聞き覚えのある声にそちらを見れば司と冬弥が何やら話しているところだった。
興味ないな、と足早に通り過ぎようとした時である。
「…彰人に捧げた心臓はいつか返して貰わなければいけなかったんです。それが、今になっただけで」
「…しかしなぁ」
「…。…すみません」
何か言いたげな司に冬弥が頭を下げた。
それを一瞥し、彰人は止めていた足を踏み出す。
「…なんだよ、それ」
喉の奥から絞り出した声は誰にも届かなかった。
届きさえすれば変わったかもしれないのに。
足を踏み出す方向が違えば、未来は変わっていたかもしれないのに。
「…オレは冬弥の考えを止める気はない。だが、それで良いのか?お前の、お前だけの気持ちはどうなる。…一緒に歌った時の冬弥は楽しそうだったぞ」
「……俺、は…っ!」
冬弥の答えを聞くことがなかった彰人には、もう彼の『返事』を知る術は、ない。
「やあ、東雲くん」
「…なんスか」
ひらりと手を振る人物に彰人は胡乱げな目を向ける。
対してその人物は気にした様子もなかった。
「少し、練習前に聞きたいことがあってねぇ」
「…オレに答えられることなんてないッスよ」
「おや、そうかな?」
簡素な彰人のそれに類が笑う。
何なんだ、と睨めば、彼は笑みを浮かべたまま口を開いた。
「…青柳くんとこのまま別れてしまって良いのかい?」
「…。…オレには、関係ないんで」
「…本当に?」
切り上げようとした彰人に類が問うた。
反論しようとして言葉が詰まる。
本当は。
…本当は、如何したいんだっけ。
RADWEEKENDを超える。
その為に、如何したかったんだろう。
冬弥の歌声が聴こえてくる。
彼の歌が好きだった。
ずっと、ずっと、初めて聴いた時から…ずっと。
ずっとこれからだったのに。
これから、『だった』のに。
彰人が吼える。
ぐにゃりと、視界が歪んだ。
違う、だって、このセカイは。
「…っ、オレは二度もあいつからさよならなんて言わせねぇんだよ!!!」
ぼんやりと目を覚ます。
「む、起きたな、彰人!」
「おはよう、東雲くん」
「…。…何でいんだよ…」
元気な司と隣で笑みを浮かべる類に、彰人は心底うんざりした顔をした。
あまり夢見が良くなかったのに、勘弁してほしい。
「冬弥が心配していたからなぁ、無碍には出来んだろう。まあ大切な相棒の元気がなければ心配もするのではないか?」
「ああ。青柳くんが最近君がオーバーワーク気味だからと気にしていたからねぇ、様子を見てくるように提案したのさ」
「そりゃ、どーも」
口々に言う司と類に形式だけのお礼を告げた。
確か冬弥は図書委員の活動中のはずである。
それなのに心配してくれたのだろうか。
「愛されているなぁ、彰人は」
「大切にしなよ、東雲くん」
「んなもん、言われなくても」
大声で笑う司と何かを含んだような類に彰人はあっさりと言った。
そんなこと、言われなくてもわかっている。
あんな思いは一度だけで充分だ。
戻りたい、と願って再度手に入れた位置である。
夢であったって、彼からのさよならなんてもうごめんだ。
二度と、離してなんかやらない。
雨ごときに、冬弥を渡してはやらない、と。
「オレたちは、ずっとこれからなんでね」
彰人は挑戦的に笑った。
ずっとこれからだったのに、なんて後悔はしない。
冬弥の、綺麗な歌声と相棒の位置はずっとずっと自分だけのものだ。
渡せと言われたって、渡しはしない。
だって、雨は上がっているのだから。
愛していたいのはどうして?
愛されたいのはどうして?
そんなの、知らない。
曖昧な答えは直して、一つの解に導いていく。
それは、きっと。
(オレが、そうしたいんだから、仕方ねぇだろ!)
「…なぁ、アンタら今放課後って何してる?」
「?何を今更。ワンダーステージのショーキャストだが?」
「まだ寝ぼけているのかい?それとも、リアル過ぎる夢だったのかな」




![【糖質オフの豆100%麺】 ZENB ゼンブ ヌードル 丸麺 8食 (2袋) そば パスタ ラーメン [ 糖質オフ グルテンフリー 糖質制限 腸活 時の 食物繊維 補給に ダイエット 時の栄養補給に 置き換え たんぱく質 低GI 鉄分 レンジ 調理可 ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51edkb6tLSL._SL160_.jpg)
![Barilla(バリラ) BARILLA パスタ スパゲッティ No.5 (1.78mm) 5kg [正規輸入品] イタリア産](https://m.media-amazon.com/images/I/41d5Rm8ZYTL._SL160_.jpg)
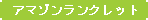
 RSS
RSS
コメントを書く...
Comments